AI時代の「頭のよさ」を再定義する。「答えがない時代」にEC運営でも必要な力とは?【ネッ担まとめ】

生成AIが日常に溶け込み始めた今、人間にとっての「頭のよさ」とは何でしょうか? そんな問いに真正面から向き合った対談がありました。今回の「ネッ担まとめ」では、「知識の量」や「正解スピード」では測れなくなった時代の知性と、そこから見えてくるAIとの付き合い方を考えていきます。
試されるのは「脳の持久力」
AI時代における「頭がいい」とはどういうことか? 気鋭の脳科学者・毛内拡氏に聞く | AGENDA Note.
https://agenda-note.com/brands/detail/id=7353
毛内 AI時代に、脳はどう使われるべきなのかをずっと考えていました。今までは答えがある問いに対して素早く解を出せることや、知識がたくさんあることが頭の良さの象徴でした。しかし今は、それらの力はあまり必要なくなってきています。
むしろ、答えがないことに取り組んでいく力が重要です。
(中略)
萩原 私は武蔵野美術大学で講師をしていますが、「答えがない時代に、いかに持久力をもって考え続けられるか」は、美術教育でも強く重視しています。
萩原 生成AIが日々進化する中で、人間の「頭がいい」状態について、もう少しご説明いただけますか。
毛内 まず、AIを使いこなす能力は重要になってくるでしょう。私たちがAI時代に育んでいかなければいけないのは、コミュニケーション能力だと思います。きちんとプロンプトを書けるというのも結局、AIとのコミュニケーション能力ですよね。
(中略)
コミュニケーションにはマニュアルがあるわけではないので、柔軟に言葉を選んだり、顔色をうかがったり、いろいろしなければいけない。答えがないことに取り組むのと同様に、これにも脳の持久力が試されます。
単に「プロンプトが書けるかどうか」ではなく、「プロンプトに必要な『意図』を言語化できるかどうか」が問われているわけです。これはまさに、コミュニケーションの本質と重なります。
AI時代のコミュニケーション力とは、「伝える力+構造化+想像力」のかけ合わせ。もちろん人間同士の関係性においても、この「伝え方の設計力」が今後ますます成果の差につながっていく気がします。
要チェック記事
1時間で4000着 米国版シーイン「 サイダー 」がZ世代の心を掴んでいる理由 | DIGIDAY
https://digiday.jp/glossy/the-strategies-behind-ciders-millions-of-monthly-sales-to-gen-z/
そもそもの世代差は埋められない戦略なので、30代以上の経営者は若い担当者にマーケティングを任せた方がいいと思った。
90歳になっても締め切りは絶対守る…「怠け者」の直木賞作家が編み出した"すごいスケジュール管理法" | PRESIDENT Online
https://president.jp/articles/-/103311?page=1
世代やトレンド、テクノロジーは進化していくけれども、自分に合ったノウハウは何歳になっても磨けるし、生き続けるわけだ。
日本から消えた「コーリン鉛筆」がタイで復活…年1億本売れる国民的ブランドに育てた"破天荒な元社員"の執念 | PRESIDENT Online
https://president.jp/articles/-/103097
実績うんぬんよりも、すごい人生。こんなドラマティックな展開に憧れてしまうけれど、自分じゃ絶対に耐えられないっすわ。
「コンサルタント」にとって重要な5つの心構え | PRINCIPLE
https://www.principle-c.com/column/seo/consultant-mindset-five-principles/
同じ仕事を続けている人間として共感。特に「前へ動かせ」。コンサルタントの仕事はチームに進んでもらうこと。進めば視界が大きく開けます。
まずWhyより始めよ──継続的に成果を出すためのマーケティング思考 | Web担当者Forum
https://webtan.impress.co.jp/e/2025/10/22/50222
「何をやるのか(What)」だけでなく、「どうやるのか(How)」までAIが提案してくれる時代。「なぜやるのか(Why)」がより大切な時代になりますね。
“究極の待ち時間” エレベーター広告で指名検索数が7倍に PeopleXの戦略を探る | ITmedia マーケティング SPECIAL
https://marketing.itmedia.co.jp/mm/articles/2510/10/news003.html
「時間を奪わず、時間を活かす広告」。最初に見たときは「なんじゃこりゃ」と思ったエレベーター広告ですが、すっかり一般化しましたね。
今週の名言
AIを育てるつもりが、逆に自分が育っていた話 | オーリーズBLOG.
https://allis-co.com/allisblog/11991/
いろいろトライしてみて次第に見えてきたのは、AIを自分の分身にするためには、自分自身がAIに任せられるだけの力を持っていなければならないということでした。
AIに業務を代替させようとするとき、必要なのはツールの知識よりも、自分の仕事をどこまで構造的に理解しているか、そして暗黙知を言語化する力です。
(中略)
そこで始めたのが、AIとの対話を通じて自分の考えを整理することです。
「この業務をAIに任せるには、どんな情報を与えればいいか」
「なぜ自分はその順番で考えていたのか」
「アウトプットの質を左右する重要な要素は何か」こうした問いをAIに投げてもらいながら、自分の思考を言葉で解きほぐしていきました。
「AIとの対話」が、結果的に「自分自身の思考整理」になっている。私自身もまったく同じことを思っていました。
誰かに説明するため、伝えるために自分の頭の中を構造化する――この作業こそが、実は一番の学習なんですよね。「AIを育てる」という発想から「AIに自分の輪郭を映し出してもらう」という発想への転換。AI時代の自己理解とは、こういうことなのかもしれません。
AIは「Google検索の代替ツール」ではありませんよ!!
ECマーケティング人財育成は「EC事業の内製化」を支援するコンサルティング会社です。ECMJコンサルタントが社内のECチームに伴走し、EC事業を進めながらEC運営ノウハウをインプットしていきます。詳しくはECMJのホームページをご覧ください。
UdemyでECマーケティング動画を配信中です。こちらもあわせてご覧下さい。
ユウキノインは寄り添い伴走しながら中小企業・ECサイトのSEOからコンテンツマーケティング、プレスリリースやクラウドファンディングなど集客・販促・広報をお手伝いする会社です。詳しくはユウキノインのホームページをご覧ください。
Designequationは何かに特化したサポートではなく、モール・ベンダー選定や広告・CSなど各企業に合わせたカスタマイズ型の運用サポートを行っています。
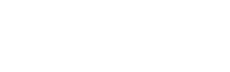
正解があるものは、すべてAIに任せられる時代になりつつあります。
人間に残されるのは「これが正解です」というゴールの存在しない課題。そこに求められるのは、「ではどう考えるのか?」という問いに応える力です。
特にECやマーケティングの現場では、正解のない打ち手や、顧客心理のゆらぎに向き合う場面が増えています。だからこそ、数字の分析やPDCA以上に「考え続ける力」や「違和感を探し続ける力」が重要になります。