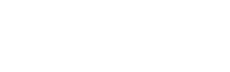EC業界で市場価値を最大化する――「全体を見渡せる人材」になるためのキャリア設計
EC市場が拡大する一方で、「年収が上がらない」「キャリアアップの道が見えない」と悩むEC担当者が増えている。EC業界の発展・成熟に伴う業務の細分化で、「部分的な経験しか積めない」という状況もその一因になっているという。激変する環境のなかで、EC人材はどうキャリアを築けばいいのか。成長企業の代表とEC業界の専門家が、現代のEC人材がめざすべきキャリアパスを徹底解説。さらに、実際にキャリアアップを果たしたコマースメディア社員3人の実例も紹介する。

EC業界の専門家が対談、見えてきた課題と市場価値を高めるためのヒント
EC人材がスキルアップや成長を求められる現代において、どのようなキャリアパスを描くべきか。コマースメディアの井澤孝宏代表とデジタルコマース総合研究所の本谷知彦氏の対談から現状の課題、「制作」「運営」「マーケティング」の3要素に分解したEC人材の可能性と限界、そして市場価値を高める道筋を探ってみる。
EC業界におけるキャリアアップの難しさ
――EC業界でのキャリア形成について、どのように捉えていますか?
コマースメディア 井澤孝宏代表(以下、井澤代表):従来、EC事業は実店舗や本業の補助的な位置づけと見なされることが多く、社内でのEC担当者の地位が低く見られがちでした。コロナ禍を機に状況は変わりつつありますが、小売市場全体で見れば、未だにECを重要部門と捉えていない企業も少なくありません。
そういった状況下でEC部門の担当者は業務範囲が広い傾向にあります。そこで弊社(コマースメディア)では、その幅広い業務内容やスキルを正当に評価し、待遇を向上させる取り組みを進めています。

EC事業成功の難易度上昇と人材不足の深刻化
――EC業界の専門家として、EC市場とEC人材の課題をどのように見ていますか?
デジタルコマース総合研究所 本谷知彦代表(以下、本谷氏):EC事業が成功する難易度は近年、劇的に上昇しています。その大きな要因は、過去20年間で小売市場は1.25倍の伸びにとどまる一方で、EC市場規模は9.3倍に拡大し、伸びしろが以前より少なくなっている点にあります。コロナ禍での事業者増加、ネット広告市場の規模が20年間で20倍になるほどの激しい広告合戦などでEC市場は過当競争状態、EC事業の難易度を高めていますよね。
さらに、スマートフォン・SNSの浸透による消費行動の多様化、オムニチャネルの重要性、物流・決済といった周辺要素の進化、AIの登場など、時代ごとに積み重なる要素もECビジネスをどんどん難しくしています。

井澤代表:ECの黎明期(1990年代後半~)は、EC事業を0から立ち上げ、全体を経験できた時代でした。しかし、現代はすでに事業として確立された大規模EC部門に配属されることが多く、分業制のため一部業務以外の経験を積めず、0から100までのEC業務を一連で経験できる機会が圧倒的に少なくなっています。こうした事情から、特に若手層においては、EC業務全体を管掌できるような多岐にわたる経験を持つ人材が少ないのが現状ではないでしょうか。
本谷氏:EC担当者のキャリア形成を阻む要因として、日本はリアル店舗が強すぎる流通構造の問題もあると感じています。EC化率が低く、リアルチャネルなしでは売り上げが伸びにくい状況ということですね。そのため、リアルチャネルが優先されEC事業に十分な投資がされないケースは少なくありません。
井澤代表:十分な投資予算がなければ、販促や広告運用も経験できませんよね。そもそも、EC事業が期待されていないケースがあり、身動きが取れずに苦しむ担当者が多いと感じています。また、EC担当者の多くが事務作業に追われがちで、収益を生む業務を経験できない状況もあります。
本谷氏:自社ECに加え、各ECプラットフォームで運営方針やルールが異なり、頻繁に変わります。そのため、出店しているEC事業者の業務はとても複雑化していますよね。日々の作業に追われることがキャリア形成を阻む1つの要因にもなっているでしょう。
井澤代表:その他のキャリアの壁として、商材や業務の縦割り、実務経験不足が挙げられます。特定の商材や一部業務(例:「楽天市場」運用のみ、広告運用のみ)に特化し、キャリアの幅が広がらないケースが多く見られます。また、大手企業では実務を外部に委託し、担当者は指示出しのみで実務経験が不足し、将来のキャリアに不安を感じることも少なくありません。
EC人材のキャリアパス
――IT業界やWebマーケティングの業界に比べて、EC人材のキャリアパスは明示されていないように感じます。どう考えるべきでしょうか?
井澤代表:私はEC業務を「制作」「運営」「マーケティング」の3要素に分解して考えています。そのなかで、それぞれを「スペシャリスト」として極めていくか、「全体を統括」するかでキャリアパスが変わります。
本谷氏:IT業界のように明確な専門性と資格がひもづく業界に比べて、ECではマーケティング、物流、クリエイティブといった専門領域の境界があいまいになっていたり、専門領域が存在するにもかかわらず、実施体制があいまいになったりしているケースは多いと思います。しかし、数年後にはEC領域の専門性も明確化され、一部に特化した「スペシャリスト」の重要性が認識される時代になるでしょう。そのため、スペシャリストをめざす人は自身の技術を磨き続けることが重要です。
井澤代表:AIの登場で今後、EC業務が「意思決定や思考する部分」と「手を動かす作業の部分」に切り分けられていくと予想しています。スペシャリストは「何かを決められる、基準を作っていける人」はキャリアを構築できるでしょう。特に私は、「運営」の領域に注目しています。マーケティングや制作には情報や基準が豊富にあるのに対し、運営はまだ未知数です。優れた運営の定義は明確ではないですよね。各事業者の手法がまだ確立されていない未開拓領域が多いからです。深く極めると面白い領域になると考えています。
制作とマーケティングは「合わせ技」が重要になるでしょう。単体で専門性を極めるだけではキャリアのアッパー(上限)が訪れてしまう可能性があり、他分野とのコミュニケーションや付加価値をどう作れるかが鍵になる。特に制作はプラットフォーム側で作りやすくなっているためかなり成熟しています。以前よりも制作単体の市場単価は下がっています。
ECは商売です。収益を伸ばすために、3つの要素のどれかが欠けても成長できません。1つの領域だけ極めても、それが他の要素にどう影響を与えるか? 結果的に収益の最大化につながらなければ意味はありません。そのため、スペシャリストであっても1つの領域を極めるだけでなく「他領域への理解」が、自身の市場価値アップの分かれ道になるでしょう。
ECの3要素を統括する人材の市場価値とキャリアの可能性
――ECの3要素(制作、運営、マーケティング)全体を理解し、統括する人材についてはいかがでしょう?
井澤代表:統括できる人材は非常に少ないのが現状です。各領域の売上・利益への貢献度が「測れない」「測っていない」企業がほとんどであり、売り上げに直結するマーケティングに焦点が当たりがちです。しかしながら、ECはモノを扱うため、全体を俯瞰し判断できる統括人材がいないと、成長が鈍化したり「大きな事故」につながったりするリスクがあります。

本谷氏:ECは1人の「営業のスーパーマン」が売り上げを稼ぐビジネスではなく、「全体としての仕組みで利益を出していく」ものであり、そこを俯瞰してコントロールできる統括人材の役割は非常に大きいものです。そのような人材は経営からの信頼も高まります。
井澤代表:私の場合は、2016年のコマースメディア創業前にEC事業の責任者としてすべての業務に携わっていた経験が、まさに経営に近いものでした。資金調達以外はすべて関わり、採用、事業計画(損益計算書の作成)、人員配置、仕入れ、商品開発まで経験できる点がEC事業の面白さです。ただし、広くいろいろ取り組む経験にはバランスが重要です。大手企業出身者のなかには、実務のほとんどを外注企業にアウトソーシングし、各業務の「質を評価できる」レベルに達していないケースがあります。そこまで業務に深く携わらないと、真の質を理解することは難しく、真に統括できる人材は希少であるため、その市場価値は高くなります。
本谷氏:EC事業の統括が経営に近いという視点は、EC人材のキャリア形成において極めて重要な意味を持ちます。ただ、EC事業は多岐にわたる要素で構成されており、それらを俯瞰し有機的に結びつけてコントロールするテクニックはかなり難しいのが実情です。その能力を持つ人材は他のビジネスと比較しても重要で希少性があります。そのため、コマースメディアのような専門企業が人材の育成、キャリアを支援する意義はとても大きいです。
井澤代表:ECを統括できる人材は、資金調達を除くと小さな会社の経営者と同じです。任されたECサイトの将来を構想し、それに必要なリソースをすべて調達する責任を負います。損益計算(PL)の管理、戦略立案、チームマネジメント、KPI設計といった経営者としてのスキル習得が含まれるからです。
私自身、「楽天市場」のECコンサルタント時代を経て、ベンチャー企業でEC事業をゼロから立ち上げました。カスタマーサポートなどのフロント業務からスタートし、最初の半年間は失敗の連続で、独学でサーバー知識やサイト構築を学び、商品登録、撮影などもすべて1人。その後、デザインやエンジニアリングの人材を採用し、3年間でEC規模を10億円ほどに成長させた経験は、まさに小さな会社の経営そのものだったと言えます。
こうした「全体を見渡せる人材」を育てるために、コマースメディアでは独自の育成方針を掲げています。部署で縦割りにせず、メンバーには幅広い業務を担当してもらう体制です。幅広く業務を経験することと、特定領域を深掘りすること、その両方を評価しています。たとえば、クライアントに対してコンサルティングができても、実行するための運営の理解がない人材は評価しません。また、現場の業務を理解し、各業務の「質を評価できる」人材のみがマネージャーになれる仕組みです。統括できる人材、他領域への理解がある人材を正当に評価することで、市場価値の高いEC人材の育成をめざしています。
「支援側×事業側」を同時に経験できるまれな環境とは? 実践事例に見るECキャリアパスのロールモデル
ここからは、前半で語られた「スペシャリスト」「EC統括」のロールモデルとなるコマースメディアのスタッフに、これまでのキャリアや働き方などについてインタビューする。
コマースメディアは、「クライアントのEC総合支援」と「自社ブランド運営」という支援と直販の両方を手がけるEC総合企業。支援事業では、有名メーカーやキャラクターグッズのECを制作から運用・物流までワンストップで支援。Shopify Premier Partner企業でもある。自社のEC事業を運用する「事業会社側」、EC事業者の運用をサポートする「支援会社側」の両方の経験を積めるというまれな環境が、EC人材の多様なキャリア形成を可能にしている。

「未経験→EC統括」の成功モデル:小林俊也氏
小林俊也氏は、ECの実務は未経験でコマースメディアに入社し、クライアントの支援業務からスタートし、現在では育児用品を中心に扱う自社事業「Poled(ポレッド)事業」の責任者に就任。オフラインも含めて統括している。ECスキルの習得プロセスは、梱包・発送から受注・出荷、CS、モール・自社サイト販促PR活動へと段階的にステップアップ。その過程でPLの作成、MD(マーチャンダイジング)、輸入関連業務にも携わり、商品のビジネスサイクル全体をマネジメントする能力を養った。

小林氏:コマースメディアでは自身のキャリアアップのための壁を感じることがないため、他の責任者がいても新たな事業や役割に挑戦し、無限大なキャリアの広がりを追求できます。
複数のプロダクトやブランドの数値を分析し、EC事業運営の「勘どころ」を養う上で、コマースメディアで培う「ECの支援側」の経験が非常に役立っています。自身の実績では、多角的な視点から「Poled」の売り上げのアッパーを見極め、「楽天市場」や「Amazon.co.jp」などといった特定のモールでの集客に固執せず、ブランド認知拡大といった戦略的な選択を可能にし、実際にPR施策で指名検索数を前年対比130%に増加させ、売り上げも伸ばしました。「Poled」を上場規模にまで成長させた経験を生かし、他の事業も立ち上げていくことが次の目標です。
また、EC担当者のキャリアや給与UPについても、特定の販路で無理に売り上げを上げて利益を削るのではなく、PRやMD軸も含め事業全体で売り上げを上げられると交渉しやすくなると思います。単一モール担当の方は売上UP施策に限界があるので、運営できる販路を増やしたり、他販路にも生きるPRやMD施策に挑戦していきましょう。

https://shop.poled.co.jp/
「広く浅い『何でも屋』」「実務経験の少なさ」からの脱却:西塔美波氏
西塔美波氏は、前職の中規模家電メーカーでSNS、EC、営業と幅広い業務をこなす「何でも屋」的な役割だったゆえに、実務経験が「広く浅くなってしまっていた」ことに課題を感じていた。特に、SNSやPR企画は1人で担当していたことから業務の多くを代理店に依頼せざるを得ず、自身の「手を動かして実務を積む経験が不足している」ことを気に病んでいたという。EC事業規模が小さく成果が数値化できない点もコンプレックスだった。

西塔氏:コマースメディア入社後、この課題を克服し、実行力を大きく向上させました。最も大きな変化は目的を達成するための企画から実行、効果測定まで一連の流れを自分で進行できるようになったことです。「Poled」での大規模なタイアップ企画では、リサーチから企画立案、投稿内容作成、効果測定まで一貫して手がける経験を複数積み、大きな自信と成長につながりました。
コマースメディアでは「ちょっとやってみて」と任されることが多く、当初は不安やプレッシャーを感じたものの、「失敗しても良い、挑戦を評価してくれる」という社風が成長を後押ししたと思います。これまでは1つのブランドを中心に担当していましたが、今後は社内で運営する他のブランドのメンバーと連携しながら、PRやSNS運用のノウハウを横展開する体制作りに挑戦していきます。
コマースメディアで実行力を高められたのは、前職での1人担当としての責任感が生きていると感じています。任された仕事に対して「自分で考えてやり切る」姿勢を持つことが、結果的に業務の幅を広げ、専門性を高めるためにも大切だと思います。
複数の事業会社のEC責任者を経験し、すでに経験豊富な人材のさらなる成長モデル:中村亮氏
前職ではライフスタイル雑貨のEC責任者を務め、ECの豊富な実務経験を持つ中村亮氏。前職の事業会社で特定のプロダクトに限られたECを運営しているだけでは今後のキャリアに制約があると感じ、より「幅広くいろいろなプロダクトや領域」に関わりたいと支援会社への転職を決意した。コマースメディアを選んだ決め手は、井澤代表の「ECは小売・流通である」というマーケティングなどのテクニック先行ではないECに対する考え方に共感したこと。入社後は、支援側と事業会社側、両方の経験を積めるキャリアパスの価値を経験している。

中村氏:自社事業では「Poled」事業でEC責任者を務めています。「Poled」事業は流通額も大きく、事業会社の大規模ECでしかなかなか得られないプロモーション、外部ツールや外部委託の活用にも前職と変わらず携わることができています。
コマースメディアは、自身のキャリア上では5社目です。ライフスタイル雑貨の事業会社では6年間EC事業の責任者を務めました。一方、ECの支援事業は入社前までは未経験でしたが、本谷氏と共に、ECビジネスの課題を解決するための戦略立案を支援する「グロース分析」サービスの立ち上げを担当し、コンサルティングや営業にも関わることができています。
コマースメディアでは、事業会社でできることに加え、事業会社にいた時にはできなかった経験もできているため、日々自身の成長を感じています。
前職・コマースメディアへもECの責任者として転職していますが、初めてECに携わるようになった会社で、制作・運営・マーケティングの各業務領域の実務を経験し、売上責任も担ってきた経験が生きていると感じています。
EC業界で責任者としてキャリアアップしていくためには、複数業務領域の実務を経験することと、売上責任を担う経験をすることがポイントだと思います。
「全体を見渡せる人材」として市場価値を高める戦略とキャリアパス
EC業界の人材不足が深刻化し、同時にEC事業成功の難易度も上昇するなか、「全体を見渡せる人材」になることで市場価値を高めることができる。後半では、井澤代表と本谷氏の対談で触れられた、キャリアアップをめざすEC担当者が持つべき視座、アクション、求められるマインドについて伝える。
「7つのレイヤー」で考える――EC人材に求められる統括的視点
――キャリアアップをめざすEC担当者が持つべき視座について教えてください。
本谷氏:キャリアアップ、スキルアップのカギは「他の分野も見渡せるマインドを持っているか」「それを上司が見極められるか」にあるでしょう。ECに携わるさまざまな業務について、それぞれを切り分けて考え、個別具体的にアプローチする考え方が重要です。
その業務について、私はECを統括する上で持つべき視点として、自身の経験から導き出した「7つのレイヤー」を提唱しています。

「戦略」「MD」「チャネル」「マーケティング」「IT」「オペレーション」「体制」を7つのレイヤーに分け、これらをバランスよく俯瞰し、常に連携させることが重要だと考えています。その上で「全体を見渡せる人材」となるためには、次の3つがポイントになります。
- 時間軸で物事を捉える力
- 今なすべきことと、3年後、5年後を見据えた上でなすべきことを区別し、戦略的に考える
- 3C(Customer、Company、Competitor)の理解
- 市場、自社、競合を深く理解し、ECの成長につながるための根幹となる視点を持つ
- テクニカルとファンダメンタル、オペレーションとストラテジーの区別
- スペシャリストが陥りがちな「小手先のテクニカルな解決」に終始せず、事業の根本や戦略を深く考える視点を持つ
井澤代表:業務全体を見渡せる人材は「EC統括」に限った話ではありません。スペシャリストにも同じことが言えます。全体を見渡す力を持った上で各分野を極め、「他領域への理解」と「他領域との合わせ技」ができるスペシャリストは希少価値が高いのです。一方で評価できる人がそもそも経営側にいないという構造的な課題もあります。
本谷氏:日本のEC業界の歴史がまだ浅く、多くの経営層が60代、70代でECを理解していないということも一因にありますよね。「ネット通販」という言葉が、従来の新聞広告などによる通販の延長線上にあると誤解されがちで、経営側がECの本質を理解できないことから、適切な評価が難しいのが実情です。
また、マーケティング担当者の存在感が強すぎるというケースも少なくありません。ECとそれ以外の事業を手がける企業において、経営層によるECの理解が不十分なことが多いからこそ、ECのなかだけでも統括性を高められる人材が重要になります。
しかし、今後10年、20年と時が経ち、ECに馴染んだ世代が経営層になるにつれて、EC人材のキャリアはより明確に描かれるようになるでしょう。少子高齢化による実店舗の維持困難化が必然的にECシフトを加速させ、EC市場はまだまだ伸びていきます。これはEC人材にとって追い風になると思います。

今すぐ取り組むべきキャリアアクション
――キャリアアップのために求められるアクション、マインドは。
井澤代表:ゼロから経験することですね。もし現在の会社で新たなEC事業の立ち上げ機会があれば、それに積極的に取り組むことを推奨します。事業立ち上げのチャンスがなくても、本谷さんが提唱していた7つのレイヤー(「戦略」「MD」「チャネル」「マーケティング」「IT」「オペレーション」「体制」)のなかで、自分が経験していない分野に業務を広げることが重要です。いきなり転職して環境を変えるのではなく、転職せずに慣れた環境でそのような経験を積むことに勝るものはないです。
もしそれが難しい場合は転職も視野に入れ、さまざまな事業や販売チャネルを展開している事業会社を選ぶことを推奨します。複数のブランドやジャンルを扱っている企業であれば、幅広い経験を積む機会が得やすいでしょう。代行会社では業務が細分化されており、幅広い業務に携わるのが難しい場合が多いです。これまで経験がない、まったく異なるジャンルの事業会社に挑戦することも有効な選択肢でしょう。EC事業への期待や投資の状況、分業の体制も経験できる幅に影響するため、面接などを通して確認することをお勧めします。

本谷氏:キャリアアップする際に最も重要なのは、「指導して任せられるマインド」を持てるかどうかです。統括者は、部下やスタッフを適切にコントロールし、チーム全体や組織全体の成果に価値を見出し、そして失敗した際には責任を取る「覚悟」が求められます。
井澤代表:その点、コマースメディアはメンバーの業務を限定せず、新しい業務や役割への挑戦を積極的に促すことで成長してきました。
そもそも、EC事業に携わることには、他の業態にはない大きな可能性があります。
EC事業の責任者は、実店舗の店長に似ていますが、決定的に違うのは経験できる売り上げの規模です。ECにはエリアによる物理的な売り上げのアッパーがなく、億単位の売り上げを経験できる可能性もあります。年商10億円規模のECを経験することは、日本企業の上位10%に入る規模のビジネスを回していることに等しく、これはまさに小さな会社の経営そのものです。
EC事業に携わる人は、「ものすごく可能性を秘めたことをやっている」という自覚を持ってほしいと思います。繰り返しになりますが、EC事業全体を運用する経験は経営に極めて近い能力を育むため、そのキャリアはもっと尊重され、市場のなかで価値が出てくるはずです。
EC業界の成熟は、業務の細分化と担当範囲の限定化を生みましたが、同時に「全体を見渡せる人材」の希少性を際立たせました。部分的な経験から脱却し、「全体像を捉えることのできるスペシャリスト」「『最小単位の経営』を担えるEC統括」をめざすことで、その先のキャリアを築いていけるでしょう。
EC業界で価値あるキャリアを築きませんか?
コマースメディアでは、EC担当者がこれまでのキャリアを生かし、事業側と支援側の両方で活躍できる環境を提供している。部署の垣根を越えて新規事業を含む幅広い業務にチャレンジでき、これまでのキャリアを最大限に生かしながら、さらなる成長を実現できる。
自発的に業務に携わり、自身の活躍の場を積極的に広げる意欲と成長意欲がある人物を求めている。メンバー個々の「自立と自律」を重視しており、成果を出すための柔軟な働き方が可能。
リモートワークやフレックスタイム制を活用し、通院やお子さんの送迎をしながら効率的に業務を進めているメンバーも多数。
このシリーズのバックナンバー:
- EC業界で「成長」「活躍」「スキルアップ」できる人物とは? 転職者+担当者が語る現場の実態【コマースメディアの例】2023/9/19公開
- 転職者が「ECの知見が高まる」「成長できる」「働きやすい」と話す会社はどんな職場ですか? コマースメディアのコンサルタントに聞いてみた【探訪記】2023/10/10公開
- ECの構築から運用まで「全体を考えられる制作担当者」が活躍するコマースメディア。専門スキル+運営知識をアップしている転職者に職場環境を聞いてみた2024/2/29公開
- メーカー出身者も活躍! 転職者がEC業界のキャリアアップでコマースメディアを選ぶワケとは? 活躍中の社員に「成長できる職場」「働き方」のリアルを直撃インタビュー2025/1/29公開