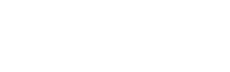AI時代に起きる購買行動の“地殻変動”。エージェントコマースから選ばれるブランド、ECサイトになるには?

米国に本社を持つ世界有数のグローバル経営コンサルティング会社Kearney(カーニー)のレポートによると、「エージェント型コマース」モデルは、商品がどの順番で表示されるかを決定するのは消費者ではなく、アルゴリズムになっているそうです。Kearneyのレポートから、AI時代に小売事業者が勝ち残るためのポイントを解説します。
AIがもたらす購買行動の変化
AIは、消費者の買い物の仕方、そして市場における小売事業者の競争環境を変えています。Kearneyの調査によると、AIによって動作する「ショッピングエージェント」が、これまで人間が行っていた購買判断を引き継ぎ始めていることがわかりました。

「この大きな変化が、EC小売事業者と消費者の関係において、大きな転換をもたらすだろう」とKearneyは警告しています。
Kearneyのレポートによると、AIシステムがユーザーのニーズを先読みし、価格を比較、自動で購入する仕組みの「エージェント型コマース」は、すでに概念から現実の仕組みへと急速に移行していると言います。
Kearneyが2025年7月と9月にそれぞれ750人の消費者を対象に実施した2回の調査によると、米国の消費者の10人中6人が、「今後1年以内にAIショッピングエージェントを使うようになる」と答え、約4分の3の消費者がすでにAIツールに親しんでいることがわかりました。
自社ブランドが「購買の意思決定プロセスに登場するか」が争われる時代
Kearneyの消費者・小売部門のパートナーであり、レポートの主執筆者であるキャサリン・ブラック氏は次のように話しています。
エージェント型コマースは、ECの黎明期以来、かつてない形で「購買の仲介構造」を変えてしまうでしょう。もはや、チャットボットやアプリを運用しているかどうかではありません。問題は「自社のブランドがAIエージェントの意思決定プロセスにそもそも登場するかどうか」なのです。(ブラック氏)
鍵はアルゴリズムからの信頼獲得
ブラック氏は、この変化を「購買判断における影響力を誰が握るか、という意味で購買決定の“地殻変動”が起きている」と指摘しています。
エージェント型コマースの世界では、商品がどの順番で、どの価格で表示されるのかを決定するのは、もはや消費者ではなくアルゴリズムです。何十年もかけてブランドロイヤルティを育ててきた小売事業者は、これからはアルゴリズムからの信頼を築かなければならないのです。(ブラック氏)
4つの消費者タイプによるAIとの関わり方
Kearneyの調査によると、消費者によるAIとの関わり方には、異なる4つのタイプがあります。
- タイプ1:テクノロジーの活用に積極的で、AIを早期に取り入れるタイプ。消費者のうち約15%。AIを使って日常の作業を自動化し、時間を節約している。
- タイプ2:実用的かつ価格に敏感なタイプ。同35%。割引や節約につながることがAIを使う動機になっている。
- タイプ3:プライバシーを重視する、AIにすべての意思決定をゆだねることは懐疑的なタイプ。同30%。自分が意思決定の主導権とデータの透明性を保てる場合にのみAIを使う。
- タイプ4:従前のルーチンを重視し、AIよりも、慣れ親しんだブランドや人間とのやり取りを好むタイプ。同20%。
消費者のタイプごとにこうした違いがある一方で、Kearneyは全ての消費者に共通する欲求として、「賢い買い物客」でありたいという傾向も確認しました。つまり、AIに買い物を代行させたとしても、お得な買い物ができたことの証明、支払いの限度額の設定、目に見える予算管理を求めるということです。
AI時代の市場で起きている変化
消費者の購買行動だけでなく、小売事業者による市場競争の構図も、同様に急速に変化しています。Kearneyによると、AIが浸透し始めた市場で優位性を持ちつつあるのは、「ChatGPT」「Google Gemini」「Klarna(クラーナ)」「Instacart」といった「スーパーエージェント」たちです。これらは複数の小売事業者のデータを集約し、横断的に取引を行うプラットフォームです。
本当の“買い物カゴ争奪戦”は、「Walmart 対 Target」のような小売企業同士ではありません。AIエージェントを手がける「OpenAI 対 Google 対 Klarna」 なのです。消費者が最も求めているスピード、価格、信頼を提供できるのは、これらのテクノロジー企業が提供するプラットフォームだからです。(ブラック氏)

消費者がAIを選ぶ理由
信頼性の高さが、消費者が購買の過程でAIを取り入れる大きな理由です。特に医療や美容分野でその傾向が顕著です。調査では、70%以上の回答者が「AIエージェントに、より安価な処方薬や健康関連商品を見つけてもらえると思っている」と答えました。
美容分野は、いわば炭鉱のカナリアです。もしAIが消費者のスキンケア選びを便利で簡単にできるなら、栄養、金融サービス、医療にも容易に拡大できるでしょう。消費者が小さな買い物をエージェントに任せることに慣れれば、やがて大きな買い物も任せるようになります。(ブラック氏)
小売事業者に予想される変化
AIエージェントが起点となるコストの増加
その影響は小売事業者の財務面でも大きいといいます。Kearneyの試算によると、価格の透明化、注文数の減少、そしてエージェントプラットフォームの手数料によって、小売事業者はEBIT(利払前・税引前利益)が最大で500ベーシスポイント(=5%)減少する可能性があります。
また、平均販売価格は約8%下落し、フルフィルメントコストは注文数の減少・小口化により10〜15%上昇。さらに、代理店プラットフォームが取引ごとに約4%を手数料として徴収する可能性があると推定しています。
同時に、小売事業者ではマーケティング予算もエージェント側へ移行すると予想されています。
消費者に代わり、ほしい商品の発見をAIエージェントが支配するようになると、広告予算は小売事業者のリテールメディアネットワークから、より上流のプラットフォームへと移っていくでしょう。新しい“店舗の入り口”は、小売事業者の自社ECサイトでもアプリでもありません。顧客が最初に目にするものを決めるアルゴリズムなのです。
次世代の小売戦争は、クリック数や商品棚の取り合いではありません。AIエージェントに選ばれる“アルゴリズム上の優位性”をどのブランドが確立できるかの戦いになるでしょう。(ブラック氏)
市場競争で勝つためのアルゴリズム対策
小売事業者が市場競争で生き残るために、Kearneyは「agent-preferred(AIエージェントに好まれる)」なブランドになるよう提言しています。つまり、AIアルゴリズムが購買の提案を行う際に選ばれやすいブランドになるということです。そのためには、次のアクションが求められます。
- アルゴリズムが読み取りやすいように商品データを構造化すること
- 在庫の可視性を高めるためのオープンAPIを整備すること
- 価格の透明性を確保すること
- 信頼性の高いフルフィルメントを維持すること
Kearneyの分析によると、エージェント型コマースは企業にとって大きなチャンスであると同時に、試練でもあります。消費者はAIエージェントを通じて、ショッピングの際の利便性と購買の意思決定の決定権を得る一方で、小売事業者は利益率の縮小と、AIが主導する市場において、自社ブランドが表示されなければ存在感を失うリスクに直面します。
ブラック氏は最後にこう警告しています。
AIエージェントが市場に浸透する世界は、多くの人が予想するよりずっと早く到来しています。顧客の半分がAI経由で買い物をするようになったとき、自社ブランドがどのように認識されているかを理解していない小売事業者は、すでに取り残されているのです。(ブラック氏)