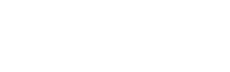データ活用を習慣化する+「再現できるヒント」をつかめるようにするために必要なこととは?

「EC事業を内製化する」――それは必ずしも、「Webサイトやコンテンツの制作スキルを身につける」「リスティング広告の運用を自社内で行う」「自社サイトのシステム改修をECチーム内で解決する」ことを意味しません。ECに関係する専門的な領域は、すでにいち担当者の努力でどうにかなる時代ではなくなっています。
EC事業の内製化を目標に、ECマーケティングに関係するテーマを設定、その判断をするための「考え方」を伝えていきます。20回目の連載は「データ活用の“習慣化”の壁を越える」をテーマに解説します。
ここをクリックで連載の目次を表示
- 連載第1回~14回はこちら
- 売上UPにつながる要素を探すためには、日々の行動とデータをつなげることが大切!
- 突然、セッション数が爆増&売上もUP! こんな「異変」を教えてくれるのがデータです。継続確認してないとチャンスを逃すかも?
- データを活用するための考え方「的当てゲーム理論」と「データは宝の地図じゃなくて、コンパス」とは?
- データを見て「傾向が見えた気分」になっているあなた! 数字から「背景」と「変化」を見ることが大切なんです
- データ活用を習慣化する土台作りはとってもシンプル。毎日5つのデータ項目を確認+「改善・施策」「理由・特筆事項」を記載するだけ!
ECのマーケティングは「ヒト・モノ・カネ・情報といった自社のリソース」と「外部のマーケティングソリューション」を組み合わせて、「結果としての売り上げと利益を最大限に伸ばす」ことが求められます。
つまり「EC事業の内製化」とは「業務の内製化」ではなく、「判断の内製化」なのです。ECの戦略・方針、日々のアクション・行動、そしてソリューションの選択が成果につながっているか、これだけは社内のネットショップ担当者でなければ判断ができません。
「強いEC会社を支えるネットショップ担当者を作る人財育成講座」では、ECマーケティング人財育成(ECMJ)が、こうした判断を行えるEC担当者育成に向けたポイントを解説します。
「数値管理表」を毎日記入できるようになるコツとは?
 ネッタヌ
ネッタヌ石田さん、こんにちは。先月教えてもらった数値管理表、早速試してみましたよ!
 石田
石田ネッタヌ君、こんにちは。ちゃんとやってみたんだね、ありがとう。
う~ん……。でも、表を見せてもらった感じだと、ちょっと不十分な気がするなぁ。
 ネッタヌ
ネッタヌうっ……バレてしまいましたか。
実はデータのところは数日分をまとめて記入しちゃっていました。「改善・施策」も少しは書いたんですが、「理由・特筆事項」はまったく埋められませんでした(汗)
 石田
石田そうでしょう。実際、たった5つのデータ項目と2つのテキスト項目――それだけの表なんだけれど、「毎日つける」となると、急にハードルが上がるよね。
今回、ネッタヌ君が直面したのがまさに「最初の壁」なんだ。 つまり、「シンプルでも毎日やり続けるのは難しい」。
 ネッタヌ
ネッタヌたしかに、やってみて改めて思いました。単に毎日つけるだけでも意外とハードルが高いです。特に「改善・施策」と「理由・特筆事項」を書くのは、どうしても後回しになっちゃって。
 石田
石田これってネッタヌ君だけじゃなくて、どの会社でも最初にぶつかる「壁」なんだ。どんなにシンプルな仕組みでも、それを「毎日やる」ってなると別問題だよね。だからこそ、「数値管理表=データ活用」を「習慣」にしていくための工夫が必要なんだ。
運用する時間を「先に確保しておく」ことが大切
 ネッタヌ
ネッタヌ毎日無理なく続けるコツってあるんでしょうか?
 石田
石田大事なのは「数値管理表に向き合う時間を、あらかじめ確保しておく」ことなんだ。営業日の毎朝15分、チームで「数値管理表を運用する時間」を固定で取っておく。
 ネッタヌ
ネッタヌなるほど!「先に時間を取る」って、言われてみると当たり前だけれど、そこが抜けていました。
 石田
石田たとえば毎朝朝礼をしている会社なら、その流れで行ってもいいと思う。とにかく、「いつやるか」を先に決めておくことが最大のポイントなんだ。
 ネッタヌ
ネッタヌ次にその15分で何をするか、ですね。
 石田
石田まず数値管理表に5つのデータ項目を入力する。これは共通のデータだから、1人が担当すればOK。複数のショップを運営している場合は、必要に応じて分担していこう。
 ネッタヌ
ネッタヌデータ部分は代表者が入力すればいいんですね。じゃあ、「改善・施策」と「理由・特筆事項」はそれぞれの担当ですか?
 石田
石田そのとおり。「改善・施策」は、自分が担当している業務で「昨日やったこと」を記録する。たとえば「メルマガを送った」「商品ページを直した」「新しい広告を出稿した」。そういった「アクション」を書く。
 ネッタヌ
ネッタヌあとは「理由・特筆事項」。
 石田
石田「理由・特筆事項」は、「自分たちがやったことではないけれど、起こったこと」を書く。たとえば、「モールのキャンペーンがあった」「お客さまから珍しい問い合わせがあった」「高額のまとめ買いがあった」とか。
「想定外からのインパクト」を記録する欄ってことだね。自分の業務エリアで気づいたことがあれば、それをぜひ入れておいてほしい。
 ネッタヌ
ネッタヌ「改善・施策=自分の行動」、「理由・特筆事項=外からの影響」ってことですね!
「なぜその数値になったのか」を話し合い、習慣化&再現する方法を探せるようにする
 石田
石田そしてデータとテキスト部分の入力後、残りの時間で、チームで集まって「なぜこの数字になったのか?」を話し合ってほしいんだ。
 ネッタヌ
ネッタヌ「売り上げがなぜこの金額だったのか」「コンバージョン率がなぜ高かったのか」とか?
 石田
石田そうそう。たとえば、前日の売り上げが100万円で2日前が50万円だったとする。「なんで?」って疑問がわくよね? セッションが増えた? 単価が上がった? 大口注文があった? それを仮説として会話しながら探していく。
 ネッタヌ
ネッタヌでもそれって、理由がわからないことも多そうですね。
 石田
石田もちろん、全部が全部、理由がわかるわけじゃない。でもね、これを毎日繰り返していると、「数字が変化したときにモヤモヤする」感覚が育ってくるんだ。
 ネッタヌ
ネッタヌモヤモヤ、ですか?
 石田
石田たとえば、前日の売り上げが急に跳ねたのに、理由がわからない。すると、「なんで?」って考えずにいられなくなる。この「モヤモヤ」が出てきたら、習慣化としては大成功。理由が気になって仕方なくなると、人は自然と理由を探すようになるんだ。
 ネッタヌ
ネッタヌ気持ち悪いから、探さずにいられない!
 石田
石田そして、少しずつ理由を見つけられるようになってくると、今度は「じゃあそれを再現できないか?」と考えるようになる。
 ネッタヌ
ネッタヌ再現!!!
 石田
石田データの要因を特定して、それを再現可能な形にできれば、強力な武器になる。もちろん全部が再現できるわけじゃないけれど、再現できるものもある。それができれば「他社にはない強み」が育っていく。

毎日行う理由は「習慣になる」「データの変化がわかるようになる」から
 ネッタヌ
ネッタヌ毎日やることって、やっぱり大事なんですね。でも、なんで「毎日」にこだわるんですか?
 石田
石田うん、理由は大きく2つある。
1つは単純に毎日やることで「習慣」になるから。そしてもう1つは、毎日やるからこそ「データの変化がわかるようになる」からなんだ。特に、重要なのが「理由・特筆事項」の欄。ここは毎日調査しないと、「なんでこの出来事が起きたか?」っていう要因が、日にちが経つほどわからなくなるんだよ。
 ネッタヌ
ネッタヌたしかに。自分たちでやったことなら日報に残っていたりしますが、「起きたこと」を探して記録しなかったら忘れちゃいますね。
 石田
石田でも、翌日だったら「あれ、昨日なんか変だったな」って気づけるじゃない。たとえば――競合商品の在庫切れだった、前日にテレビで特集されていた、台風が近づいて防災の意識が高まった。こういうのって1か月後には思い出せない。
 ネッタヌ
ネッタヌ「理由・特筆事項」はフレッシュなうちに拾っておかないと、もう拾えなくなる!
 石田
石田そういうこと。だから翌日にデータを見て、「なんでだろう?」と考える時間を取ること。さらにレベルを上げるなら、リアルタイムで変化のキャッチアップができるようになると最高だね。
 ネッタヌ
ネッタヌリアルタイムって?
 石田
石田たとえば、注文が入るとメール通知が届くネットショップ、結構あるよね? そのメールが急に連続して届きだすと、「何か起きたな」ってすぐわかる。
 ネッタヌ
ネッタヌあ、それ、あります! 短時間でピコンピコンってなると、「あれ? 何だ何だ?」って思います!
 石田
石田それそれ(笑) あとは、「GA4」のリアルタイム画面をブラウザで常時表示しておく。急にセッション数が跳ねたら、何か外的な要因が起こったと思ってすぐ調査する。動いたタイミングこそ、最も調べやすいタイミングなんだ!
 ネッタヌ
ネッタヌリアルタイムで気づけたら、理由の対策もすぐにできそう!
 石田
石田これを積み重ねていくと、「なんでこのデータなんだ?」と思考を止めない体質になる。そして、数値と現象を結びつけて、「再現できるヒント」を少しずつつかんでいく、これこそがデータ活用の本質なんだよ。

「気付きのヒント」はお客さまが教えてくれるかも
 ネッタヌ
ネッタヌなるほど~。ネッタヌ、とっても甘かったです……。
 石田
石田じゃあネッタヌ君、今日の話を聞いた上で、また次の1か月、数値管理表の入力を頑張って、「データ活用の習慣」をチームに根付かせていってね。
……と言いたいところなんだけれど、最後に「気づきのヒント」をもう1つだけ、伝えておこうか。
 ネッタヌ
ネッタヌえっ、なんですか!?
 石田
石田「理由・特筆事項」。つまり起こったこと・あったことの要因をどう見つけるかが、やっぱりデータ活用のキモだったでしょ?
 ネッタヌ
ネッタヌはい! それがわかれば強いですよね。
 石田
石田でもね、実際には「なんで起きたのかわからない」ってことばかりなんだよ。注文が増えたとか、セッション数が跳ねたとか。チームの誰も心当たりがないことも多い。
 ネッタヌ
ネッタヌそういう時、どうやって気づけばいいんですか?
 石田
石田それは「お客さまが教えてくれるかもしれない」ってこと。前にも話したけど、お客さまからのお問い合わせって、めちゃくちゃヒントになることがある。
 ネッタヌ
ネッタヌうんうん。
 石田
石田たとえば、「この商品、もう少しで売り切れると聞いたんですが、在庫ありますか?」とか、「〇〇って雑誌で見たんですけれど、公式サイトで買えますか?」とかね。
こういう問い合わせが来ると、「自分たちが知らないところで何か起きている」可能性があるって気づけるよね。
 ネッタヌ
ネッタヌうわ……。それ、きちんと問い合わせを見ていないと気づかないやつですね。
 石田
石田そしてSNS。注文やアクセスが急に増えたときは、X(旧Twitter)で検索してみると、ヒントが落ちていることもある。自社のブランド名や商品名、ジャンル名などをエゴサーチして、「何か語られていないか?」をチェックする。
 ネッタヌ
ネッタヌこれはもう探偵ですね、もはや(笑)
 石田
石田そして、もうワンステップ上の方法として「お客さまに直接聞いてみる」ってやつ。
 ネッタヌ
ネッタヌ電話するってことですか!?
 石田
石田「今回ご注文いただいた商品って、どこで知っていただいたんですか?」って。そうすると、「有名なインスタグラマーのライブで紹介されていましたよ」とか教えてくれたりする。
 ネッタヌ
ネッタヌ自分たちじゃ絶対見つけられないやつですね!
 石田
石田そうなんだよね。リアルなお客さまの声って、データの何倍も濃い情報を含んでいることがある。「お客さまに連絡するなんて……」と思う人も多いけれど、だからこそ逆にライバルと差がつくんだ。じゃあ、今回はここまでにして、次の1か月「気づきの種」を拾ってきてください!
 ネッタヌ
ネッタヌネッタヌ、頑張ります!
ECマーケティング人財育成は「マーケティングチームの内製化」を支援するコンサルティング会社です。ECMJコンサルタントが社内のECチームに伴走し、EC事業を進めながらEC運営ノウハウをインプットしていきます。詳しくはECMJのホームページをご覧ください。