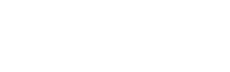「決済が通らない」で失うのは売上と信頼感。EC事業者と消費者への調査から見えたリアルな実態と対策のヒント

「理由もわからずエラーになる」「決済が通らない」。こんな経験していませんか?
「カートに商品を入れて購入ボタンを押したのに、決済が通らない」――そんな体験をしたことはありませんか? クレジットカード情報に誤りはないはずなのに、理由もわからずエラーになる。この「なぜか買えない」という違和感は、ユーザーにとって購入に向けた大きな心理的な壁でなると同時に、EC事業者にとっては売上機会損失につながる重大なリスクです。
日々の買い物などもオンラインにシフトするなかで、クレジットカード決済の“非承認”という見えにくい障壁が、購買体験と企業の売り上げにマイナスの影響を与えるケースも少なくありません。特に高額商材や急ぎの購入時には「通らない=買えない」が即時の機会損失に直結し、事業者にとっては広告投資や集客努力を無駄にしてしまう結果にもなりかねません。
YTGATEはこうした決済の実態を可視化するため、2025年5月に消費者とEC事業者向けの2つの調査を実施しました。そのなかから特に注目すべき結果を抜粋し、両者間に横たわる認識のギャップ、そこから導かれる課題・打ち手について考察します。
「決済エラー」は珍しくない――3か月以内に約3割のユーザーが経験
YTGATEが全国の20~60代のオンラインショッピング利用者・男女302人を対象に実施した調査では、約30%(89人)が「過去3か月以内に決済の失敗を経験した」と回答しました。つまり、3人に1人が直近でトラブルを経験している状況です。

さらにその影響は感情面にも及びます。決済エラー経験者のうち、約29%が「イライラ・怒り」を感じたと答え、5.6%は「そのブランドやECサイトからの離脱を検討した」と回答。 購入完了直前のエラーは、ユーザーの購買意欲を損なうだけでなく、企業やブランド全体への不信感にもつながりかねません。

行動面にも分岐が見られました。決済エラー経験者のうち約28%は、別の手段で購入を継続した一方で、約8.6%は「購入をやめた」「他サイトを利用した」と回答しています。つまり、およそ1割のユーザーが他社へ流出している可能性があります。

加えて注目すべきは、「なぜエラーになったのかが不明なまま」というケースが多い点です。 決済エラーを経験したユーザーのうち、約半数が「理由が表示されなかった」「わからなかった」と回答している結果も得られました。

この不透明さこそが、ユーザーの不信感や離脱意欲を高めてしまう要因であり、EC事業者にとっては知らぬ間に売りなっている売り上げとして、深刻に捉えるべきポイントだといえるでしょう。
「重要な課題」だが「詳しく知らない」。意識と理解のギャップ
YTGATEが実施したEC事業者309人(年商100億円以上の大手企業を含む)への調査では、クレジットカード決済における決済承認率(オーソリ承認率)について、7割以上のEC事業者が「自社にとって重要な課題」と認識していることが明らかになりました。

しかしその一方で、62.4%が「(決算承認率という)言葉の意味を詳しく知らなかった」と回答。課題意識は高まっているものの、具体的な改善に向けた知識・手段は浸透していないのが現状です。

特に年商規模による差も見られ、年商100億円以上の企業では「内容までよく知っている」が約3割に達する一方で、年商10億円未満の企業では「知らない」割合が顕著に高いという結果に。 つまり、大手は経営指標として扱い始めている一方で、中小企業ではそもそも気づいていないケースも多いのです。

加えて、全体の76.5%が「決済承認率の改善ニーズがある」と回答。そのうち約25%は「非常にニーズがある」と答えています。現場で日常的に「なぜか通らない決済」に直面している企業ほど、改善による売上回復のポテンシャルを痛感していることが伺えます。

背景にある“制度変更”と複雑化するリスク判断
こうした非承認の増加には、近年の制度変更も影響しています。2025年3月から「EMV 3-Dセキュア」導入が必須化されたことで、決済時に本人認証のステップが追加され、ユーザーの手続きが煩雑になりました。
また、3Dセキュア(本人認証)を行ったうえで成立した決済が不正利用となった場合、加盟店ではなくカード会社がその損害を負担する「ライアビリティシフト」が発生します。この背景から、カード会社としてはリスク回避の観点から、少しでも不審な兆候があれば承認を控える傾向が強まっているのが実情です。
そのため、限度額が残っていても、利用地域や時間帯、決済金額、カードの種類、IPアドレス、端末情報の違いなどが引き金となり、決済が拒否されるケースは珍しくありません。
一方、EC事業者側にはこうした判断ロジックが見えにくく、「決済が行われなかった理由がわからない」「改善の余地があるのか不明」という声も多く聞かれます。結果として、カゴ落ちが発生し、顧客からのクレームが増加、社内対応の工数がかさむなど、 売り上げ、CX、オペレーションの三面でじわじわとした負荷が蓄積されているのです。
今こそ「決済承認率」を攻めの経営指標に
決済承認率は、単なるオペレーション上のKPIではありません。それは、ユーザーの購入意欲が最も高まる決済直前に立ちはだかる最後の関門であり、もしここでエラーや非承認が発生すれば、それまで積み上げてきたマーケティングや商品開発、UI改善といったあらゆる施策の努力が水の泡となってしまいます。
たとえば、広告費をかけて集客し、カート投入率やLP改善でコンバージョン率を高めても、最後の決済段階で承認されなければ売り上げはゼロ。この「見えない機会損失」を正しく把握し、戦略的に改善していくことが、これからのEC経営にとって重要な差別化要素になると考えています。
では、EC事業者はどのような対応を取るべきなのでしょうか。
EC事業者が行うべき対策をフェーズ毎に解説

クレジットカード決済には、「決済前」「決済時」「決済後」と複数のステージが存在し、それぞれに売上ロスや不正リスクの発生ポイントが潜んでいます。EC事業者が安定した売り上げと顧客体験を維持するためには、こうした決済プロセス全体を俯瞰し、戦略的に対応していくことが重要です。
具体的には、以下の3ステップを踏まえた取り組みが効果的です。
①現状把握
まずは自社の決済データを分析し、決済承認率やカゴ落ち発生率などを可視化することで、どの段階で売り上げを失っているのかを明らかにします。「ユーザーがどの時点で、なぜ購入をやめたのか」の要因を詳細に分析することで、UIや導線の最適化だけでなく、決済に起因するボトルネックの特定と解消にもつながります。
②課題の特定
不正対策が強化される一方で、過剰な防御設定により正当な取引まではじかれてしまうケースも増えています。可視化された数値をもとに、エラーコード、発生タイミング、利用カード種別などの傾向を分析し、非承認や離脱の根本要因を特定します。
③対策立案
分析結果に基づき、カード会社ごとの対応方針の調整、判定ルールや接続仕様の見直し、ユーザーへのフォロー施策など、実効性のある改善策を設計・実行していきます。
さらに、実務のなかでは次の3つの観点を重点的に見直すことが大切です。
会員情報の監視と健全化(決済前)
会員登録・ログイン・情報変更時における不審な挙動を検知し、不正アカウントの早期排除を行うことで、不正決済を未然に防ぐことができます。
決済取引のリアルタイム監視(決済時)
取引情報と決済情報を連携させ、決済直後に不正検知を行う仕組みを導入することで、不正利用を即時に遮断し、被害拡大を防止します。
決済後の離脱対策(決済後)
エラーコードなどのシステムログを分析し、エラー発生後のユーザーに対して再決済の案内やサポートを行うことで、取りこぼしを防ぎ、売り上げの回復を図ります。
これらの施策を通じて、「決済承認率」という一見地味な指標を、売り上げとユーザー体験を左右する“戦略的な成長レバー”として位置づけることができるのです。
しかし、「実際にはそこまで手が回らない」というのが多くのEC事業者の本音ではないでしょうか。売上管理、在庫対応、顧客対応、広告運用――日々の業務に追われるなかで、「決済が本当に正しく機能しているか」を継続的にモニタリングして課題を洗い出し、改善を実行していくことは、現場にとって決して簡単なことではありません。
だからこそ、私たちは“入金の入り口”である決済の現場を見守り、代わりに改善を伴走する存在でありたいと考えています。
YTGATEは「承認率の可視化」を出発点に据え、「カゴ落ち要因の分析と改善施策の立案」「不正リスクと売上確保のバランス最適化」「カード会社との交渉・対話による調整支援」などを行っています。
単なる数値の改善ではなく、その裏にあるユーザー体験や売上最大化への貢献にこだわりながら、EC事業の持続的成長を支えてまいります。
YTGATEの決済承認率改善サービス:https://ytgate.jp/service/payment/