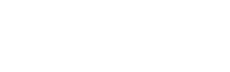データを活用するための考え方「的当てゲーム理論」と「データは宝の地図じゃなくて、コンパス」とは?

「EC事業を内製化する」――それは必ずしも、「Webサイトやコンテンツの制作スキルを身につける」「リスティング広告の運用を自社内で行う」「自社サイトのシステム改修をECチーム内で解決する」ことを意味しません。ECに関係する専門的な領域は、すでにいち担当者の努力でどうにかなる時代ではなくなっています。
EC事業の内製化を目標に、ECマーケティングに関係するテーマを設定、その判断をするための「考え方」を伝えていきます。17回目の連載は「体系的なデータ活用の考え方」をテーマに解説します。
ここをクリックで連載の目次を表示
- 連載第1回~10回はこちら
- 売れる理由を一番知っているのはお客さま、CVR評価時の注意点、情報管理の徹底――「EC事業の内製化」をめざすために必要なことを振り返り!
- EC事業に「本気で取り組む価値」とは? ECを「新しいニーズの探索」と捉えると会社を進化させることができる
- ECに取り組むことで会社のDXを促進できる! いつもアンテナを張って会社の動きを変える「新しいニーズ」に気づけるようにしよう
- 売上UPにつながる要素を探すためには、日々の行動とデータをつなげることが大切!
- 突然、セッション数が爆増&売上もUP! こんな「異変」を教えてくれるのがデータです。継続確認してないとチャンスを逃すかも?
ECのマーケティングは「ヒト・モノ・カネ・情報といった自社のリソース」と「外部のマーケティングソリューション」を組み合わせて、「結果としての売り上げと利益を最大限に伸ばす」ことが求められます。
つまり「EC事業の内製化」とは「業務の内製化」ではなく、「判断の内製化」なのです。ECの戦略・方針、日々のアクション・行動、そしてソリューションの選択が成果につながっているか、これだけは社内のネットショップ担当者でなければ判断ができません。
「強いEC会社を支えるネットショップ担当者を作る人財育成講座」では、ECマーケティング人財育成(ECMJ)が、こうした判断を行えるEC担当者育成に向けたポイントを解説します。
データ活用について考えていこう!
 ネッタヌ
ネッタヌ石田さん、こんにちは! 今回もよろしくお願いします!
 石田
石田はい。ネッタヌ君、こんにちはーー。
 ネッタヌ
ネッタヌ 石田
石田そうだね。どちらも私の「マーケティング観」を作った大事な経験で、今回はその経験も含めて導き出した「ECのマーケティングの原理原則」の話をしようか(キラリン)
 ネッタヌ
ネッタヌ楽しみです! けれど、今回のテーマの「データ活用」っていきなり言われてもイマイチピンとこないんですけれど……どこから考えればいいんですか?
 石田
石田じゃあ、まず「的当てゲーム理論」の話をしようか。マーケティングにおけるデータ活用をシンプルに理解できる考え方だ。
 ネッタヌ
ネッタヌ「的当てゲーム理論」?? なんですかそれ(笑)

「的当てゲーム理論」っていったいどんな考え方?
 石田
石田「的当てゲーム理論」は、私が2011年にECマーケティング人財育成という会社を創立してから、ずっとセミナーなどで話している理論で、ECのマーケティングにおける「行動と成果」そして「運営サイクル」の関係を説明している「型」なんだよね。
 ネッタヌ
ネッタヌ(石田さんが創業のときから話している由緒正しい理論だったんだ。「なんですかそれ」なんてバカにしてマズかったかな……)少年が1人、左側に立っていますね。
 石田
石田うん。「的当てゲーム理論」の構図を説明するね。まず、この左側に立っている少年が、ECを販売チャネルとして事業を進める人。つまり、我々ネットショップの運営者だ。経営者でも担当者でもいいと思う。そして右側には暗闇があるんだけれど、その暗闇の向こうのどこかに「的」がある。
 ネッタヌ
ネッタヌ暗闇の向こうにある見えない「的」に向かってボールを投げる、そんな的当てゲームなんですね(ネッタヌがこの前お祭りでやった的当てゲームとは少し違うな……)
 石田
石田そう。暗闇の向こうにある的に向かってボールを投げるんだけれど、当然少年からは的が見えない。
 ネッタヌ
ネッタヌじゃあ、ボールを投げても的に当たったのか見えないですよね?
 石田
石田たしかに的に当たったかは見えない。ただ、的に当たったか当たってないか、それを判断できる「何か」が返ってくるんだ。
ちょっと難しい質問なんだけれど、ネッタヌ君、何だか想像つく?
 ネッタヌ
ネッタヌう~ん、的は見えないけれど、返ってくるもの……なんだろう……。
 石田
石田それはね。「音」なんだ。ボールが的に当たったか当たってないかは見えないけれど、的に当たったら「音」が返ってくる。
 ネッタヌ
ネッタヌつまり、「音」で的に当たったかどうかがわかると。
 石田
石田ボールが的に当たらなかったら音がしないだけ。的の端に当たれば「ドスッ」と鈍い音が鳴る。そして、的の真ん中にきれいに当たれば「カコーン」って気持ちのいい音が返ってくるわけだ。
 ネッタヌ
ネッタヌつまり……。
 石田
石田この「ボールを投げる」っていうのは、お客さまや市場に対するアプローチ、つまり改善施策のことだ。そして、返ってくる「音」が「成果」。つまり、データなんだよ。
 ネッタヌ
ネッタヌなるほどー。ネットショップのマーケティングはセッション数やコンバージョン率など、成果がデータで返ってきますもんね。
 石田
石田ネットショップの運営者は、ボール(改善施策)を投げて音(データ)を聞く、そしてその音(データ)から反応を仮説検証して、次のボール(改善施策)を投げる。この繰り返しこそECのマーケティングであり、それを表現したのが「的当てゲーム理論」なんだよ。
 ネッタヌ
ネッタヌちなみに、この暗闇って何を意味しているんですか?
 石田
石田インターネットだよ。ネットショップって、お客さんの顔が見えないでしょ?
 ネッタヌ
ネッタヌあー、確かにECってそうですね。お客さんが見えない。
 石田
石田加えて、暗闇の向こうにある「的」が何か。それは「お客さん」自身なんだ。

「的」は同じ場所に留まらない。投げるボールを修正し続けよう
 ネッタヌ
ネッタヌつまり、僕らはインターネットの向こうにいるお客さんに向かって、「改善施策」というボールを投げている、と。
 石田
石田そのとおり! さすがネッタヌ君、理解が早い!
もう1つ大事なのは、この「的」は少しずつ動いているってことなんだ。的は同じ場所に留まっていてくれない。
 ネッタヌ
ネッタヌ的は少しずつ動いている……。なんだか石田さんが言いたいことがわかる気がします。
 石田
石田この「的」は「お客さん」なんだけれどさ、少し表現を加えていうと「お客さんのニーズ」なんだ。お客さんのニーズって、トレンドや年齢、ライフスタイルの変化によって少しずつ変わっていくでしょ?
 ネッタヌ
ネッタヌ確かに、昨日刺さったものは今日も刺さる可能性が高いけれど、来月も刺さるとは限らない……。
 石田
石田つまり、毎回同じところにボールを投げてもいずれ当たりは悪くなる。だからこそ、動いている的(お客さんのニーズ)に合わせて、投げるボールを修正し続ける必要があるわけだ。極端な話、ネットショップの商材自体を変えたりしてさ。
 ネッタヌ
ネッタヌ返ってくる音を聞き続けるからこそ、その変化に気づけるってことですよね。
 石田
石田「音=データ」を見続けるからこそ反応の変化に気づけるんだ。
 ネッタヌ
ネッタヌ前回の「Yahoo!ショッピング」のセッション数爆増の話、あれも音を聞いていたから気づくことができたってことですよね?
 石田
石田まさにそう。毎日同じデータを見ていたからこそ、気づくことができた。
 ネッタヌ
ネッタヌもしも、データをたまにしか見てなかったら?
 石田
石田きっと気づけなかったと思う。データが変化した瞬間を見逃しただろうし、変化から時間が経ち過ぎていて「なぜそうなったのか?」の要因も探索できなかったかもしれない。
 ネッタヌ
ネッタヌ日々の観察が大事だってことですね。

データは「コンパス」。正しい方向に進んでいるかどうかを確認するためのツール
 石田
石田あともう1つ、伝えておきたい「データ活用の考え方」がある。
 ネッタヌ
ネッタヌお、出ましたね。なんでしょう?
 石田
石田これは前回のコラムでも少し触れたことなんだけれど、「データは宝の地図じゃなくて、コンパス」なんだよ。
 ネッタヌ
ネッタヌあ、石田さん言っていました!
 石田
石田データってさ、一見宝の地図のように「ここを掘れば宝がある」って示してくれるもののように感じるじゃない。でも本当はそうじゃない。
 ネッタヌ
ネッタヌじゃあ、何を教えてくれるんですか?
 石田
石田いま自分たちが進んでいる方向。つまり、目的・目標に対して「ズレていないか、異変がないか」を教えてくれる。
 ネッタヌ
ネッタヌ正しい方向に進んでいるかどうかを確認するためのツールってことですね。
 石田
石田そうそう。だから、成果につなげるための「答え」が書いてあるわけじゃないんだ。
 ネッタヌ
ネッタヌ「コンパスで確認して、行動を修正して、また進む」――ここは完全に「的当てゲーム理論」と共通していますね。
 石田
石田まさにそこ。「的当てゲーム理論」と「データは宝の地図じゃなくて、コンパス」。ぜひ両方ともECのマーケティングチームの「共通認識」にしてほしい。
 ネッタヌ
ネッタヌ石田さん、「的当てゲーム理論」と「データは宝の地図じゃなくて、コンパス」の考え方の大切さはすごーくわかったんですけれど、これを日々の実務から習慣化していく方法ってないですかね?
 石田
石田ネッタヌ君、ナイスなところを突っ込むね。これらの「原理原則」は頭の中でわかっていても、なかなか思考には浸透していかない。実務から思考に浸透させていかないと習慣化しないし、チームの「共通認識」にはならないよね。
 ネッタヌ
ネッタヌぜひ、「実務から習慣化していく方法」のヒントを教えてもらえたら、ネッタヌ、飛び上がって喜んじゃうんですが……。
 石田
石田じゃあ、次回はこのマーケティングの原理原則をいかに「チームに浸透させるか」の話をしようか。ここがこのコラムの目的でもある「マーケティングチームの内製化」の一番のポイントになるよね。
 ネッタヌ
ネッタヌ次回もよろしくお願いします!!
ECマーケティング人財育成は「マーケティングチームの内製化」を支援するコンサルティング会社です。ECMJコンサルタントが社内のECチームに伴走し、EC事業を進めながらEC運営ノウハウをインプットしていきます。詳しくはECMJのホームページをご覧ください。