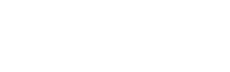ライブコマースは“リアル感”がキモ! 購入率2.7倍を実現した動画配信の秘訣をオンライン酒屋「クランド」に聞く

約500種類の自社開発したアルコール飲料などを販売するオンライン酒屋「クランド(KURAND)」。両手をついて謝る柴犬のイラストをパッケージに描いた「おわびーる」やチョコミントのリキュール「夜9時のチョコミント」など、独自性のある商品で若年層を中心に人気を集める。2025年5月に開始したライブコマースも好調で、開始から12日間で購入率が従来比270%に向上した。クランドの広報 遠山彩華氏、銭田桃歌氏、ライブコマースツール「Tig」を提供するパロニムの代表取締役 小林道生氏、カスタマーサクセスチーム リーダー 坂本晃基氏に「ライブコマース市場の盛り上がり」や「効果的な動画配信の秘訣」を聞いた。
日本のライブコマースは「第3世代」に突入、その特長は?
中国で火が着き、世界的に広がった「ライブコマース」。中国では、ライブコマースの市場規模が2018年から5年で30倍以上に成長、中国のEコマース分野の研究・コンサルティング機関「网经社」によると、2023年の流通総額は4兆5657億元(約94兆円)にのぼると予測されている(参考:网经社:《2023年(上)中国网络零售市场数据报告》)。
小林氏の見解では、日本では「Instagramライブ」が実装された2017年頃に第1世代が到来、その後、第2世代を経てコロナ禍に第3世代が始まったとのこと。「日本でライブコマースは流行らない」とも言われるが、「日本のライブコマースは中国とは異なるスタイルで独自に発展している」と小林氏は説明する。
中国のライブコマースは、「KOL(キー・オピニオン・リーダー)」が出演し、そのネームバリューを生かして集客します。商品やサービスへの信頼を「KOL」によって担保し、かつ「配信中だけの特典」として大幅割引を提供し、大量販売につなげます。ライブコマースだけをひたすら放送するプラットフォームもあり、ここにくれば「必ずお得な買い物ができる」として、絶大な人気を得たのです。(小林氏)
パロニムの代表取締役 小林道生氏
日本もそれにならって、インフルエンサーの出演で消費者を引き付け、割引販売をしてみたが、そうしたスタイルは定着しなかった。そのため「ライブコマース」という手法自体が日本市場にマッチしないと言われるようになったという。
現状、国内で主流と言われているのは、中国のようにリアルタイムで大量販売するのではなく、作り手の思いや開発ストーリーを丁寧に伝え、視聴者の質問やコメントを拾いながら相互にコミュニケーションをする配信スタイルです。瞬間的な売上増よりも、ブランディングやエンゲージメントの向上、コミュニティ形成を目的に、ライブコマースを活用する企業が増えています。(小林氏)
一部のSNSでは「購買」につながりにくい。クランドがライブコマースを導入した背景
クランドは、酒屋の息子として育った荻原恭朗氏が2013年に創業、2018年にオンライン酒屋「クランド」を開始した。自社開発のアルコール飲料を中心に、ノンアルコール飲料、おつまみ、グラスなど幅広い商品を展開する。
経済産業省が発表した「令和5年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」によれば、「食品、飲料、酒類」のEC化率は4.29%と低い。そこで、ECにおけるアルコール製品購入のハードルを下げる目的で、独自の付加価値を付与する戦略を取っている。


ネーミングや商品コンセプト、パッケージに趣向を凝らすほか、お酒をランダムに詰め合わせたセット商品「酒ガチャ」も販売。「アレルギーや苦手なものは避けられる」「過去に届いた商品は届かない」「個別で買うよりもお得」「高額商品が入った当たりが存在」など、“ワクワクする購入体験”により購買意欲をかき立てることで、好評を得ているという。
集客はほぼSNSで、Xは30.4万人、Instagramは9.6万人、Facebookは1.4万人のフォロワーを持つ。商品のアレンジなどを親近感のあるテイストで紹介し、ユーザーの投稿をリポストしたり返信したり、積極的にコミュニケーションを取ることでフォロワーを獲得してきた。時代の変化に合わせて2023年にはショート動画の配信を始めたが、狙った結果にはつながらなかったという。

動画では、色合いや香り、ユニークなパッケージなど、テキストと写真では伝わりきらない商品の魅力を伝えることに注力しています。多く視聴された動画もあるのですが、購買につながりにくい実態がありました。というのも、アルコール飲料はSNSにおける販売規制が厳しく、Instagramではアパレルのように商品のタグ付け(ECサイトへのリンクを貼ること)ができません。TikTokではアルコール飲料の販売自体が禁止されています。(銭田氏)
動画を視聴した消費者が商品に興味を持っても、一旦プロフィールに遷移してからECサイトのURLをクリック、さらに該当商品のページを探すといった二重三重の手間が発生するためCVにつながりにくいのではないかと考えた。そこで、ライブコマースの視聴から購買まで、シームレスな体験を提供するライブコマースツール「Tig(ティグ)」に着目したという。
インスタのリール動画を再利用して、購入率が「270%」に向上
InstagramやTikTokのショッピング機能が「SNS型ライブコマース」と呼ばれるのに対し、「Tig」のように自社ECサイトやWebサイトにライブコマース機能を組み込めるものは「SaaS型ライブコマース」と呼ばれる。そして、SaaS型のなかでもTigの強みとなるのが、「シームレスな購入体験」と「作業の自動化」だという。

(画像提供:クランド)
「Tig」は、配信中に画面上の商品に触れて「購入」を押すと、画面が切り替わることなく商品をカートに入れることができます。視聴体験を遮断せず購入につなげられるのは、大きな特長です。(小林氏)

配信前・配信中・配信後の作業も自動化しています。あらかじめECサイトで販売されている全商品の情報を自動で取得しているため、商品の事前登録が不要です。商品のJANコードやQRなどを読み取るだけで、配信画面に該当商品を表示できます。
また、配信後は、配信した動画をECサイト内の該当商品ページに自動で配置します。動画を再利用することでCV向上につながるためです。もし、複数商品を一度に紹介した場合は、該当商品が登場したシーンから自動的に頭出しされます。ユーザーの手間を極力なくして、離脱が起きにくいようにしています。(小林氏)
Tigでは、接客型のライブ配信に特化した「Tig LIVE」や埋め込み型ショート動画に特化した「Tig Short」など複数サービスを展開している。クランドでは、「Tig Short」を活用して、まずはInstagramで配信した15~30秒ほどのリール動画をECサイト内で再利用することに。
10本の動画をツールに取り込み、2025年5月に該当商品ページに設置したところ、設置後12日間の購入率が従来比270%に向上した。作業時間は1本あたり3分で、合計30分間で終了したそうだ。
高速でPDCAを回すため、まずは撮影済みの動画を再利用しました。短期間で購入率が向上したのは、テキストと写真だけでは伝わりきらない商品のテクスチャや味わい、遊び心のあるパッケージなど、「購入を後押しする」ような情報を補足できたためだと分析しています。(銭田氏)
他社と比較しても、クランドさんは非常に短期間で成果につなげています。シリーズものの商品では、複数商品をまとめて紹介することもあり、そのうち1つの動画を見た人が別の商品も購入するといった「買い回り」の行動も起きています。動画の完全視聴率も高く、開始当初は視聴者の約60%が最後まで視聴していました。(坂本氏)
「これほど短期間で成果につながったのは驚きだった」と坂本氏
動画配信のコツは「口下手でも素で話す」「視聴者と交流する」
想像以上の結果が出たこともあり、現在は「Tig LIVE」も導入し、1時間前後の長時間のライブコマースの配信にも積極的にトライしている。長編では「家飲みを楽しくするクラフト酒」や「新商品のクラフトビールの比較」といった企画が人気で、毎回約20種類を紹介。平日18~20時頃に配信しており、視聴者数はユニークユーザーで100人を超えることもあるという。

初期は、広報の私と商品の開発担当者など2人体制で配信を開始しました。紹介する商品ラインアップは決めているものの台本はありません。お客さまのコメントや質問を拾って、それに答えていくスタイルです。私がお客さまの目線に近い味わいの感想を伝え、原料や製法などに踏み込んだ紹介は開発担当者が行うような役割分担です。配信中や直後よりも、商品ページに設置したアーカイブ動画が購入の決め手になっていますね。(遠山氏)
クランドが配信において重要視しているのは、「双方向のコミュニケーション」と「わかりやすさ」、そして「正直さやリアル感」だという。
SNSと同じく、ライブコマースもお客さまとのコミュニケーションの場だと捉えています。商品を紹介する際、専門的な言葉を使わず、理解しやすい言葉でお伝えすることも大事にしています。たとえば、「精米具合」を「お米の磨き具合」に変換するなど。
加えて「素でしゃべる」ことも大事にしています。日本酒が大好きなメンバーが日本酒への思いを熱く語るなど、あらかじめ用意された文章ではなく、自身の言葉で伝えることで熱量がお客さまに伝わりやすくなるのだろうなと思った。私自身は、ラフな感想を心がけています。専門的なテイスティングコメントや「おいしい」と丁寧に言うよりも、直感的に「うまっ!」と伝えたり(笑)。これはパロニムさんからのアドバイスでした。(遠山氏)
自分の言葉で伝える“リアル感”を大事にしていると遠山氏
台本をカッチリ作るライブコマースは、あまりウケが良くないんです。特にα・Z世代は「ヤラセ感」を非常に嫌います。「押し売りされている」と感じた瞬間に拒絶反応が出てしまう。「すみません、今日42回噛みました」くらいでいい。
ある大手企業では、「かき氷機」を実演販売した際、最初の10分ほどまったく氷が削れないトラブルがありましたが、結果的に大盛況でした。実は、使っていた商品は店頭に並べていたもので、危なくないように刃を抜き取ってあったんです。こうしたトラブルは、むしろ場を盛り上げる材料になります。(小林氏)
「誰が出演しているか」よりも、「ヤラセ感がないか」が最も重要だと小林氏は強調する。ライブコマースがマッチしやすい領域としては、「専門知識が必要なもの」と「高額商品」をあげた。
過去に最もコンバージョンが高かったのは、「ワイン」でした。自分の好みにピッタリ合った商品を選ぼうと思うと専門的な知識が必要になるけれど、自分で調べるのは手間になる。かといって、店舗に行っても自分がほしい情報に出会えるかわからない。そうした時に、専門知識を持った人が丁寧に解説してくれるライブコマースが理解促進につながり、結果として購入に至るようです。
また、数十万円の寝具など高額商品も売れ行きがいい傾向があります。購入するかどうかを熟考するための情報を手軽に入手できるため、タイパの良い買い物体験になるのだと思います。(小林氏)
このようにマッチしやすい領域は一定存在するが、まずは気負いせずに始めてみるのが良いのかもしれない。いずれにせよ、「作り込まない演出」と「視聴者との双方向のコミュニケーション」が共通する成功哲学のようだ。