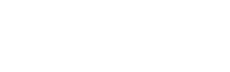先を行く米国の「ロイヤルティ」「リテールメディア」──日本と何が違う? 最新のリテールメディアのトレンドを学ぶ
米国ラスベガスで実施された小売・ブランド向けの大規模カンファレンス「SHOPTALK(ショップトーク)2025」では、「リテールメディア」「次世代検索」「ロイヤルティ」などの最新トレンドや事例が共有されたという。「SHOPTALK2025」に参加したCX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供するZETAの山崎徳之社長に、米国事業者に共有された先端トレンドなどを聞いた。数年後に日本へやってくるかもしれない米国の潮流をチェックしてほしい。

「リテールメディア」「次世代検索」「ロイヤルティ」が米国リテールでの注目ワード
――「SHOPTALK」全体の所感を教えてください。
「SHOPTALK2025」は、小売業界の最新トレンドや最新テクノロジーなどにフォーカスしたカンファレンスです。3日間で1万人以上が参加、840以上の企業が出展し、75以上のセッションが開かれました。私は3日間参加し、「リテールメディア」「次世代検索」「ロイヤルティ」の3つのトラックで開かれたセッションに耳を傾けました。
そのなかで、自社の技術レベルのポジショニング、方向性を再確認できたことに加え、ロイヤルティ、リテールメディアの展望、検索の重要性など、米国市場のトレンドを把握でき、多くの発見がありました。全体としては、「顧客体験価値(エクスペリエンス)」と「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」が重要なワードとして3日間を通して登場してきたなと感じました。単に商品を売るのではなく、顧客1人ひとりにとって最高の購買体験をいかに設計し提供するのか、そのための具体的な戦略や技術が、さまざまなセッションで熱く議論されていました。

リテールメディア:「UGC活用」が前提のリテールメディア3.0
――リテールメディアに関するセッションについて教えてください。
おもしろいと感じたのは、海外ではブランド直販ECやAmazonのようなプラットフォームも「リテール」と定義していたことです。日本の「リテール」は量販店など小売業を指すことが多いのですが、この線引きが異なりました。商品を製造し、消費者に直接「販売」するすべての接点が“リテールメディアの対象になる”という考え方が浸透していました。
この考えに基づくと、あらゆるブランドがリテールメディアのプレイヤーになり得ることを意味するのではないでしょうか。この定義の違いが、米国におけるリテールメディア市場に影響しているのだろうと感じました。
米国ではリテールメディア市場が拡大しており、ECはもちろん、店頭のサイネージなども大きく伸びています。そのため、単なる広告枠の提供(1.0)やデータ活用(2.0)ではなく、UGC(ユーザー生成コンテンツ)をいかに活用するのかという「リテールメディア3.0」が、リテールビジネスの常識として語られていたのが印象的でした。
――感じた日本マーケットとの違いを教えてください。
日本はまだデータ活用がテーマの主流になっている状況ですが、米国ではそれを超えてUGC活用やSNSとの連携などといった部分まで進んでいます。「メディアを育てて広告を掲載し、購買を促進。購入者がUGCを投稿することでメディアがさらに活性化し、より多くの広告が集まる」。こんな好循環(Media as and Commerce)を生み出す戦略が主流となりつつあります。
UGCは単なる購買後の口コミやレビューではなく、顧客を巻き込み、メディアの魅力を高め、コンテンツを永続的に豊かにしていくための「戦略的資産」として位置付けられているのです。レビューはもちろん、Q&A、顧客が投稿するコーディネート写真や使用動画など、多様なUGCがメディアの価値を向上させるという共通認識が確立されていました。
こうした部分も含めて日本のリテールメディアは、これから進化していくのではないかと感じています。
――UGCがリテールビジネスの中心となってきているような印象ですね。
あるセッションでは「Media as and Commerce(メディアとコマースの一体化)」という概念が提唱されていました。これは、次のような持続可能なエコシステムを構築する考え方です。
- メディア育成:魅力的なコンテンツ、特にUGCを核としてメディアを育て、多くの顧客を集める。
- 広告掲載:集まった質の高いトラフィックに対し、ブランドが広告を出稿し、メディアは収益を得る。
- 購買促進:広告や信頼性の高いUGCを通じて商品の購買を強力に後押しする。
- UGC生成:商品を購入した顧客が、満足度の高い体験をレビューや写真として投稿する。
- メディアのさらなる活性化:新たに生まれたUGCがコンテンツとなり、メディアの価値がさらに高まることで、サイクルが強化されながら回り続ける。
単発の広告施策ではなく、顧客をコミュニティの一員として巻き込み、一緒にメディアを育てていくというこの発想こそが、米国でリテールメディアが進化している理由の1つと言えるのではないでしょうか。
次世代検索:技術力の再確認と新たな発見
――検索に関するセッションを聞いた感想を教えてください。
ZETAがすでに提供しているテクノロジーや機能などと重なる部分が多く、日本の最先端技術が世界と遜色ないレベルにあることを再確認する機会になりました。
――興味深いセッションはありましたか?
興味深いという点では、米国では生成AIはもう検索機能に搭載されているのが大前提であり、「次世代検索」というトラックで構成されていました。「AI検索」が3つに分類され、それぞれが進化していましたね。
- 画像検索:画像から類似商品を検索する基本的な機能。
- 会話検索(Conversational Search):「友人の結婚式に着ていくピンク色のドレス」といった、より自然で曖昧な言葉での検索に対応するチャット形式の検索。
- パーソナルアシスタント:過去の購買履歴や閲覧履歴といったユーザーの行動データに基づき、検索結果を個人に最適化して提示する機能。
実はこれ、ZETAが「レコメンド検索」として提供している技術と方向性を同じくするものでした。そのため、ZETAが提供している技術レベルは海外と遜色なく、日本の企業が求める高度な検索の要求レベルは、米国とそう変わらないということがわかりましたね。
興味深い事例としては、古着アパレルEC「thredUP(スレッドアップ)」が印象的でした。古着は全てが1点ものなので、画像検索との親和性が高い領域。「thredUP」では、ユーザーが投稿したコーディネート写真から、帽子、上着、パンツといったアイテムをAIが自動でパーツ分解し、それぞれに類似した商品をECサイト内から探し出して提示するという高度な機能が実装されています。これにより、憧れの有名人が着ている高価な服と「似たシルエット」の安価な古着を探すといった、新たな発見と購買体験を生み出しています。

ロイヤルティ:3つの分類と「購買後体験(PPX)」の衝撃
――「ロイヤルティ」のトラックについて教えてください。
最大の発見があったのが、「ロイヤルティ」に関するセッションでした。米国では、顧客ロイヤルティを次の3つのレベルに細分化して捉え、それぞれに応じた施策を打つのが常識となっているようです。
- トランザクショナルロイヤルティ(取引型):ポイントや割引など、金銭的メリットに基づく関係性。より良い条件を提示する他社へ容易に乗り換えられてしまう、最も弱いレベルのロイヤルティ。
- 特長:「安さ」「お得感」を重視する顧客層であるため、獲得しやすい一方で、最も離脱しやすいのが特徴です。競合が少しでも良い条件を提示すれば、顧客はためらいなく乗り換えてしまいます。
- ビヘイビアルロイヤルティ(行動型):ブランドへの強い愛着はないものの、「店舗が近所にある」「いつも使っている」といった利便性や習慣から利用する関係性。
- 特長:この段階では、顧客は「変えるのが面倒」という心理的・物理的なスイッチングコストを感じています。そのため、取引型ロイヤルティよりも安定した関係性を築けますが、まだ「好きだから」という感情には至っていません。
- エモーショナルロイヤルティ(感情型):ブランドの世界観、哲学、提供する体験への強い愛着や共感に基づく、最も強固な関係性。Appleやパタゴニアのファンなどがこれに該当します。
- 特長:このレベルに達した顧客は、多少価格が高くても、他の選択肢があっても、そのブランドや店舗を選び続けます。彼らは単なる消費者ではなく、ブランドを応援し、自ら情報を発信する「ファン」や「伝道師」となります。これが、あらゆる企業がめざすべき最終ゴールとして位置づけられます。
特に重要視されていたのが、商品(ブランド)だけでなく、「小売(リテーラー)」に対するエモーショナルロイヤルティの構築でした。たとえば、「このブランドが好き」だけでなく、「このお店で買う体験が好き」と思わせることが、長期的な成功に不可欠だと提唱されていました。
日本で「ファン」というと、特定の「ブランド(商品)」に対する愛着などを想起しがちですが、米国では「どこで買うか(リテーラー)」に対してもエモーショナルロイヤルティを構築するという視点が強くありました。
Starbucksの事例が象徴的で、彼らが提供しているのは、コーヒーそのものの味だけでなく、「スタバで過ごす時間」という体験価値。顧客は、その体験を求めて店舗に足を運ぶ。これは、リテーラーに対するエモーショナルロイヤルティの好例です。
他にも、特定の百貨店の外商との信頼関係や、「このセレクトショップが選んだものなら間違いない」という専門店の「目利き」に対する信頼も該当します。リテーラーは、自社が提供する独自の価値で顧客の感情に訴えかけ、価格競争から脱却することが求められているでしょう。
――購買後体験も印象的だったようですね。
「PPX(Post Purchase Experience=購買後体験)」という概念が頻繁に語られていたのも印象的ですね。迅速な配送、簡単な返品プロセス、そして心躍るような開封体験といった購買後のあらゆる接点で顧客満足度を高めることが、ロイヤルティ構築に直結するという考え方です。
人気アーティストのコンサートチケットのような「お金では買えない特別な体験」をポイント交換の景品に設定することで、顧客の熱狂的な支持を集めている企業もありました。
UGCも購買後体験やロイヤルティに貢献するといったことも指摘されていました。購入後のフォローメールでレビュー投稿を促し、投稿者にはポイントを付与する。さらに、そのレビューが他の顧客の役に立つことで、投稿者は「コミュニティに貢献している」という満足感を得ることができる。この一連の流れが、顧客をファンへと昇華させる強力なエンジンとなっていくようです。
日本のリテールがめざすべきこと
米国リテール業界が「エクスペリエンス」と「パーソナライズ」を軸に、より高度な顧客関係の構築へと舵を切っていることがわかりました。
- リテールメディアの進化:データとUGCなどを活用してトラフィックを獲得、リテールメディアを持続可能なエコシステムとして構築しようとする狙いがあります。
- リテールメディアとロイヤルティで著しい進化:次世代検索の技術レベルでは日米に大きな差はないものの、リテールメディアやロイヤルティの分野では、米国がより洗練された戦略的フレームワークを構築しています。
- UGCの戦略的活用:UGCはもはや単なる口コミではなく、メディアを成長させ、顧客との感情的なつながり(エモーショナルロイヤルティ)を深めるための最重要コンテンツと位置づけられています。
日本のリテール業界に携わる方は、こうしたポイントは押さえておきたいところではないのでしょうか。米国ですでに確立されつつある「リテールメディア3.0」や「3分類のロイヤルティ戦略」といった先進的な概念をいちはやく取り入れることで、競合企業などに打ち勝つことができるようになると考えます。