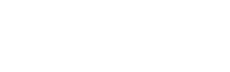「つい開いてしまった」迷惑メール、「Amazonや楽天市場のログイン通知・警告」が35%
テクノルが実施した「生成AIを悪用した迷惑メール被害とその対策」に関する実態調査によると、約4割が迷惑メールを「つい開いてしまった」「開きそうになった」といった経験があると回答した。 開封してしまった迷惑メールの主な特長は、「宅配便の不在通知」「Amazonや楽天市場のログイン通知・警告」など。調査対象は回答時に5年以上オフィスワークをしている会社員であると回答した23~59歳のモニター1020人。調査期間は2025年8月14~15日。
約6割が「迷惑メールが増えた」と回答
迷惑メールの受信件数の変化について聞いたところ、「明らかに増えた」が31.9%、「やや増えた」が29.4%で、合計6割以上が「増えた」と回答。一方、「減った」と答えたユーザーは1割程度で、迷惑メールの被害を実感しているユーザーが増加している。

迷惑メールの受信件数が「明らかに増えた」「やや増えた」と回答したユーザーに、「5年前と現在の迷惑メールの受信件数」を聞いたところ、5年前は「週に10件程度」が最多で29.6%、次いで「週に50件程度」が20.3%、「ほとんど受け取っていない」が16.2%だった。現在は「週に50件程度」が最多の27.0%、次いで「週に100件程度」が19.4%、「週に200件以上」が16.3%だった。
5年前、「週に100件程度」「150件程度」「200件以上」と回答したユーザーの合計は全体の18.9%だったが、現在ではその割合が49.3%となり、5年前と比べて30ポイント超増えた。以前は5人に1人程度だった「週に100件以上の迷惑メールを受け取る人」が、現在では2人に1人程度に広がっている一方で、「ほとんど受け取っていない」と答えたユーザーは、5年前の16.2%から現在は0%に減少した。
テクノルは「迷惑メールの送信ボリューム自体が増えていると同時に、AIなどを用いた高度な自動化・大量配信技術の影響も否定できない」と解説している。

約4割が迷惑メールの開封経験「あり」
迷惑メールを「つい開いてしまった」「開きそうになった」といった経験について聞いたところ、「何度かある」が26.7%、「一度だけある」が11.1%で、合計37.8%が実際に迷惑メールを開いた、または開きかけた経験があることがわかった。
また、「心当たりはないが不安はある」が33.9%で、直接的な被害経験がなくても、不安を抱えるユーザーが相当数いることが明らかとなった。テクノルは「メールを開く前の見極めが非常に困難になっている」と考察している。
前問で「何度かある」「一度だけある」「心当たりはないが不安はある」と回答したユーザーに、「つい開いてしまった」「開きそうになってしまった」迷惑メールの特長について聞いたところ、最も多かったのは「宅配便の不在通知(佐川・ヤマトなど)」が40.0%、次いで「Amazonや楽天市場のログイン通知・警告」が34.8%、「一見自然で信じてしまいそうな文面」が32.4%だった。
テクノルは「日常的に利用する宅配業者やECサイトを名乗ると、警戒心が薄れ、思わず開封してしまう可能性が高まる。さらに『一見自然で信じてしまいそうな文面』が上位にあがっていることから、実在する企業の通知メールを模倣し、あたかも本物のように装う巧妙さがうかがえる」と推測している。

最近の迷惑メールの印象について聞いたところ、最も多かったのは「昔より手口が巧妙化していると感じる」が49.7%、続いて「本物そっくりで見分けがつかない」が31.5%、「文章が自然で一瞬信じてしまう」が27.0%だった。テクノルは「こうした傾向の背景には、AI技術の進化によってメールの文章や体裁が洗練されてきていることも関係している」と考察している。
AI関連の巧妙なメールが増えているが、それを感じたことがあるかを聞いたところ、「とても感じる」が21.4%、「やや感じる」が48.5%で、約7割が何らかの変化を実感していることがわかった。

迷惑メール対応の現状「“完璧ではない技術”を“人の目”で補填」
迷惑メールを現在「ほとんど受け取っていない」と回答したユーザー以外に、迷惑メールの対応が業務にどのくらい影響を与えているかを聞いたところ、「非常に影響している(業務が中断する)」が9.0%、「やや影響している(集中が途切れる)」が36.8%で、約半数が業務への何らかの支障を感じていることがわかった。
テクノルは「このような影響が日常的に積み重なることで、生産性の低下やストレス増加につながるリスクも考えられる。迷惑メールへの対応は単なるIT部門の対応範囲にとどまらず、組織全体で取り組むべき経営課題のひとつ」と言及している。

勤務先で導入されている迷惑メール対策は、最多が「メールソフト(Outlookなど)の迷惑メールフィルターを利用」で45.4%、次いで「セキュリティソフトに付属のメール保護機能を使用」が26.5%、「ウイルス対策付きのクラウドメール(Google Workspace、Microsoft 365など)を利用」が17.1%だった。一方で、18.4%が「特に対策は取っていない」と回答した。
「特に対策は取っていない」と回答したユーザー以外に、対策に対する課題感を聞いたところ、最多は「完全には迷惑メールを防げない」で46.8%、次いで「通常のメールも誤ってブロックされる」が21.2%、「フィルターの設定や運用が難しい・属人化している」が18.6%、「手動で仕分けや確認が必要で手間がかかる」が15.8%だった。
テクノルは「導入は進んでいても、現在の対策は“完璧ではない技術”を“人の手”で補っている状態であり、日常業務のなかで継続的なストレスや業務効率の低下につながっている」と解説した。

求められるのは人的エラーと負担の軽減
今後、迷惑メール対策に求められる対応は、「AIによる高度な自動検知・フィルタリング」が最多の36.5%、「社員一人ひとりのセキュリティ意識向上」が30.6%、「人が判断しなくても止められる全自動フィルター」が26.2%だった。
テクノルは「ヒューマンエラーを減らし、判断や対応にかかる負担を軽減したいというニーズが強い」と推測している。

調査概要
- 調査期間:2025年8月14日~15日
- 調査方法:インターネット調査
- 調査対象:調査回答時に5年以上オフィスワークをしている会社員であると回答した23~59歳のモニター1020人
- 調査元:テクノル
- モニター提供元:PRIZMAリサーチ