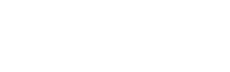【EC新時代の戦略】なぜ今“動画コマース”なのか? 変わる購買行動+施策の設計ポイント+ユニクロの事例+成功・失敗要因を解説
買い物の仕方、変わったと思いませんか? 「気になる商品を動画で見て、ついポチッと」──そんな経験がある人も多いはずです。今、ECは“読む”から“見る”、そして“買う”へと変わりつつあります。
こうした背景を踏まえると、単なるプロモーション用途にとどまらない「動画コマース」の導入が、EC事業者にとって急務となっていると言えます。動画コマース市場の現状とギャップ、視聴者の心理誘導、導線設計、成功企業の共通点や失敗パターン、そしてすぐに始められる実践アクションまでを解説します。
ECの新潮流“動画コマース”
動画が消費者の購買行動を後押し
コロナ禍以降、消費者の購買体験は大きく変化。外出自粛によって自宅で過ごす時間が増え、動画視聴が日々の生活に浸透し生活の一部となりました。結果として、「見る」だけだった動画が「買う」に直結する流れが加速。ベクトルグループが2025年に実施した調査※1では、普段よく視聴するYouTubeチャンネルなどで紹介されて知った商品やサービスについて、43%が「購入・利用したことがある」という結果が出ています。
※1:キーワードマーケティング「YouTubeでの動画視聴を通じた購買行動に関するアンケート調査結果」(調査期間:2024年12月18日~2025年1月1日、調査方法:クラウドワークスを活用したインターネット調査)

各国市場に見るグローバルの動画コマース
中国ではライブコマースがすでに巨大産業に成長しており、2017年はわずか約392億円の市場規模でしたが、2023年には同約98兆円にまで達しました※2。そこで生まれる数億円単位の売上事例は枚挙にいとまがなく、消費者も日常的に「ライブ配信を見て買う」ことに慣れ親しんでいます。
※2:China's Live Commerce Data Report 2023(出典元:100ec.cn、取得元:Statista)
一方、米国や欧州では「TikTok」や「Instagram」のショッピング機能が急速に浸透し、短尺動画からそのまま購入ページに遷移できるUXが標準化しつつあります。たとえば、米国の大手小売事業者Walmartでは、スタッフ自身がライブコマースに登場し、商品デモや使い方をわかりやすく紹介。ライブ視聴中のチャット機能を生かして、視聴者とのやりとりも交えながら、購入へ自然に誘導しています。

成長段階にある国内ライブコマース市況
対して日本のライブコマース市場は、2022年時点で約2992億円と、中国の1割にも満たない規模にとどまります。その要因として、決済手段の不足や物流対応の遅れ、さらには社内の体制整備が追いつかないなど、複合的な課題が存在します。
しかし、この“ギャップ”こそが、大手企業や先進的な中小EC事業者にとって成長機会を秘めています。まだ市場が成熟しきっていない日本だからこそ、小規模なテストと継続的なPDCAで“勝ちパターン”を探る価値があるのです。

「見る」から「買う」へ。動画が果たす転換点
動画コマースを成功させるには、視聴者の心理に沿った施策の設計が欠かせません。ここでは、次の3つの心理効果を組み合わせる方法を紹介します。
単純接触効果(ザイオンス効果)
同じ映像やメッセージを繰り返し目にすることで、視聴者はその商品やブランドに対して自然と好意を抱くようになります。たとえば、シリーズ化されたショート動画や、配信前に予告クリップを複数回配信するといった繰り返しのタッチポイントを設計すると、「いつもの動画」として視聴者の日常に定着しやすくなります。
フット・イン・ザ・ドア
まずは「いいね!」や「フォロー」「コメント」といった、視聴者が抵抗なくできる小さなアクションを促します。ここでエンゲージメントを高めることで、その後に「購入」などのより大きな行動を引き出しやすくなります。たとえば、動画中盤で「この商品に関する質問があればコメントをどうぞ」と呼びかけ、最後に「今すぐ購入はこちら」というCTAを提示する流れです。
メンタルシミュレーション効果
視聴者が頭のなかで「自分がその商品を使っている場面」をイメージすると、実際の購買行動につながりやすくなります。動画内で具体的な利用シーンを丁寧に見せることで、この効果を高めましょう。たとえば、調理器具であれば、料理をしているシーンを“手元”にフォーカスしたクローズアップで見せ、「これなら自分にも使えそう」と視聴者に感じさせます。

海外の事例をあげると、フランス本社の化粧品メーカーL'OREALでは、美容インフルエンサーや一般ユーザーが自社製品を使っている様子をショート動画で紹介し、視聴者が自分の生活に重ねて想像しやすいよう工夫しています。
こうした“自分ごと化”を促す映像演出によって、商品の魅力を直感的に理解してもらい、購入への心理的なハードルを下げる効果があります。
これらの心理効果を組み合わせることで、視聴者は「見る」だけの立場から、自然に「買う」行動へと移行します。営業の現場で用いられることが多い「段階的提案」の考え方を、映像コンテンツに応用しているイメージです。ぜひテスト配信の際に取り入れてみてください。
また、UI/UXの設計も見逃せません。モバイルで視聴されることを前提に、画面下部にワンタップで購入ページへ誘導するボタンを固定表示したり、画面遷移を最小限に抑えた導線を設計したりすることで、視聴から購入までのハードルを徹底的に低減します。こうした細かい工夫がコンバージョン率に大きく影響を与えるのです。
テスト配信時に意識したい5つのポイント
|
BtoBtoCモデルの可能性──モール型、D2C型で配信スタイルを使い分け
近年注目を集めているのが、ECモールと自社直販サイトを組み合わせたBtoBtoCモデルです。まずECモール内でライブ配信することで、既存の会員基盤を活用しつつ「場の信頼」を最大化できます。
たとえば、大手ECモールが開催したライブイベントでは、開始5分以内に視聴者の半数がチャットに参加し、即時購入ができるリンクから成約(購入)に至った事例も報告されています。
一方、メーカー直販ではブランドストーリーをじっくり語るライブ配信が有効です。映像を通じて「誰が」「どのように」商品を作っているかを可視化することで、消費者のファン化を促進し、リピート購入率を向上させることができます。
配信パートナーを選ぶ際も、フォロワー数だけでなく「同ジャンル商材で実際に成果を出した実績」を重視すると、成果の再現性が高まります。

業界動向から読み解く成功要因と失敗要因
ライブコマースで成果を上げる企業には、共通して「双方向コミュニケーション」を重視する姿勢があります。配信中に視聴者の質問へリアルタイムで答えたり、リクエストに応えたりすることで、顧客の疑問や不安を即座に解消できるため、購買意欲が高まりやすくなります。
即時対応を実践するユニクロの事例
たとえば「ユニクロ」を運営するファーストリテイリングでは、ライブ配信で新作コーディネートの紹介を行いながら、視聴者からの質問にその場で回答できるよう、動画に出演するメインホストと裏方のスタッフで役割を分担しています。
視聴者はサイズ感やスタイリングの疑問をリアルタイムで解消できるため、まるで店舗で接客を受けているような感覚を味わうことができます。こうした「即時対応」の工夫が、ECにおいてもファンづくりや購買意欲の醸成につながっているのです。
また、こうしたやり取りで得られた生の声は、商品開発や次のマーケティング施策にもフィードバック可能です。さらに、アパレルや化粧品、食品といった“質感や使用感が重要な商材”では、動画ならではのリアルな表現力が強みとなり、視聴者はまるで試着やテイスティングをしているかのように商品を体感できます。
魅力的な配信者選びも重要です。社内の開発担当者や店頭スタッフなど、商品知識が豊富で愛情を持って語れるキャラクターを起用すると、視聴者は“専門家のおすすめ”として受け入れやすくなります。加えて、ブランドと親和性の高いインフルエンサーを活用すれば、そのフォロワー層へ効率的にリーチでき、高い集客効果と宣伝効果を期待できます。
事前告知はSNSやメルマガで入念に行い、「限定割引」「数量限定アイテム」などの限定感を演出することで、視聴者の「今すぐ参加したい」という心理を引き出しましょう。
陥りやすい失敗例
一方、うまくいかないケースでは「効果測定の難しさ」が足かせになることが多いです。視聴数やコメント数は把握できても、ほかの施策との相乗効果を切り分けて売上貢献度を測定するのは困難です。
また、準備と配信の手間が想定以上にかかり、継続的な運用が途絶えてしまう企業も少なくありません。視聴者を集める事前告知が不十分だったり、機材トラブルや通信不安定で配信が途切れたりすると、ブランドへの信頼を大きく損ないかねないので注意が必要です。
このほか、配信者の力量不足やブランドイメージとの乖離も失敗要因の一つです。商品知識が不十分な配信者は視聴者の質問に答えられず、結果として離脱を招きますし、ラグジュアリー層向けの商品を安価な雰囲気で紹介すると、ブランド価値を損なうリスクがあります。
また、ほかの年代よりも視聴者が少ない高齢者層向けの商品、即効性が見えにくい商品などのライブコマースに向かない商材を選んでしまうと、いくら配信を続けても成果につながりにくいと言えます。相性の良いジャンル選定が成功の鍵です。
これらのポイントを踏まえ、継続的なPDCAサイクルと準備体制の整備を徹底しましょう。
読者への提言:今こそ“構想”から“実装”へ
これから、動画コマースに取り組むのであれば、まずは「小規模テスト」の実施をおすすめします。月に1~2回、製品詳細ページにショート動画をいくつか実装したり、短時間のライブコマースを実施して、視聴データやクリック数、購買データを収集しましょう。これらのデータをもとに仮説検証を繰り返すことで、自社に最適な配信フォーマットが見えてきます。
中長期的には「視聴完了率30%」「クリック率5%」「CVR2%」といった具体的なKPIを設定し、改めて自社にマッチする動画配信プラットフォームを選定するのが良いでしょう。社内承認を得る際は、企画書に目的・効果予測・投資対効果を明示し、マーケティング部門だけでなく、経営層や物流・システム担当部署との連携体制もアピールしましょう。
動画コマースは、単なる“動画広告”とは異なり、「伝わる」「つながる」「買いたくなる」新しい購買体験の入口です。昨日までのECの常識に、1つの挑戦を加えるだけで、明日には新しい成果が生まれるかもしれません。
次回は実際に成果を出している企業の取り組みや、より具体的な動画コマースについてさらに踏み込んでいきます。