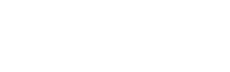SNSでの有益情報発信、楽しい読み物コンテンツ提供などの「フック集客」で自社の個性をじっくり育てる

ここではSNS、コンテンツマーケティング、プレスリリースを使った「フック集客」の方法を紹介します。広報的・間接的な要素が大きく、長期的に考えるべき「投資」です。すぐに売上につながりませんが、じっくりお店の個性を育ててくれます。
フック集客の本質
典型的なフック集客は、以下の通りです。
- SNSで日々の活動や「ユーザーにとって有益な情報」を発信
- コンテンツマーケティングでは役立つ情報や楽しい読み物を提供
- プレスリリースでは、メディアを通じて幅広い層にアピール
フック集客は、情報発信なのですが、いずれもすぐに売上につながることは、おそらくないと思います。だから取り組み順序としては、少し先です。また、商品の特性によって最適な形が変わってくるので、じっくり検討して取り組んでください。
SNSなどで、右脳的な「雰囲気」の発信
日々商品を頑張って作ったりしているシーンをショート動画にしたり、写真にしたりして発信します。「買ってください」ではなく、ふわっと「雰囲気」を発信して、ライブ感や親近感を作ります。
例えば、パン屋さんがSNSで毎日の焼きたてパンの写真を投稿したり、ブログで美味しいパンの食べ方を紹介したりするイメージです。また、海外で商品を視察しているところや自社農場で人参を収穫するところ。アウトドア用品店のスタッフが「今日のキャンプ飯」を発信するなど、プライベートのついでもよいでしょう。何か活動した時は忘れず写真や動画を撮っておくとよいでしょう。「仕事のついでのブランディング」作業です。
雰囲気を発信すると「実在感」が生まれる
このような発信は、フォロワーにとっては、いわば一瞬の工場見学や社会見学です。一度工場見学に行くとその会社の商品はちょっと自分にとって実在感のある特別な感じがしますよね。「今日も朝早くから仕入れに行ってきました!」といった投稿は、真面目な姿勢を伝えられます。
デジタルの世界でありながら温かみを感じる、この「実在感」がポイントです。「人として認識してもらえる」ことは将来的な資産です。
主な媒体はInstagramやX(旧Twitter)ですが、Facebookで友達相手に発信することも有効です。大事なのは媒体ではなく内容なので、あちこち転用していきましょう。
また、こういったSNSアカウントは顧客とのコミュニケーションツールになります。発信の合間には、時折エゴサーチをして、商品の感想を書いているお客さんにお礼や説明をするなどして、地道な関係づくりの活動もできます。またあらためて何か紹介してくれるかもしれません。
お客さんやインフルエンサーからの紹介を促進
第三者によるお店や商品についてのSNS発信を増やすためには、有償で紹介を依頼する方法もあります。インフルエンサーに依頼したり、モニターを募集して商品をInstagramで紹介してもらう「ギフティング」と呼ばれる施策です。
ただ、商品に愛着がない紹介はどうしても不自然になる恐れがありますし、広告目的であることが不明瞭な投稿をさせるとステマ規制に抵触するリスクもあるので、十分調べてから取り組んでください。
まずはあまり下心を持たないで、「自主的に紹介してくれる人との関係を育んでいく」のが一番だと思います。
記事や動画を中心に、左脳的な「情報」の発信
ブログや動画などで情報を提供する施策もよく使われています。例えば、アウトドアの楽しみ方や猫との暮らし方など、お客さんにとって役立つ情報や、楽しめる内容を提供することです。コンテンツを作ったら、前述のSNSなどでもお知らせします。媒体間の転用を意識しましょう。
コンテンツマーケティングで検索順位を上げる
特に、Google検索を考慮しつつブログなどテキストで配信することは「コンテンツマーケティング」と呼ばれます。
ユーザーのニーズや疑問に答えることをメインに考えるため、「○○したい」や「○○の意味」などを教える内容が多めになります。「毛ガニの食べ方」を見ている人は、すでに購入した人でしょう。「ナッツの健康効果」を見ている人が、即座にナッツを購入するわけではありません。
副次効果、というよりもこちらが主なメリットなのですが、コンテンツマーケティングの大きな利点は、Googleからの評価が高まって、検索順位の向上に寄与する点です。特定テーマに関する豊富なコンテンツは、そのテーマに詳しいサイトとして検索エンジンから評価されて、「毛ガニ 取り寄せ」といった買い物直結キーワードでの検索上位になります。
サイトの評価を上げていくために良質なコンテンツを増やしましょう。
他媒体での情報発信も、ブログに転用する
YouTubeなどの動画を見るユーザーは「実際どうなのかという感覚」を把握したくて調べる人が多いと思います。やってみてどうなのか、比べてみるとどうなのか、文字とか写真だけでは分からないところを把握する用途で使われます。再生回数が低くても売れます。何十回程度の視聴回数の動画で、1つ数十万円の高額な家具が売れたというケースもあります。
このように動画やInstagramで情報配信している場合も、その内容をテキスト化してブログに乗せましょう。SEO効果がありますし、コンテンツの使い回しは効率的です。
条件として、法則6でも紹介したように、Googleで評価されるためにはサイト全体の一貫性と専門性が重要になります。いわば「月刊◯◯」といった雑誌のようなイメージで、特定テーマを持っている必要があります。
「自分は何の専門家なのか」を考えつつ、情報発信をしていきましょう。
プレスリリースで、メディア掲載を促進
プレスリリースは、自分都合ではなく「メディアの都合」を考慮し、メディアが取り上げやすい形で発信することが有効です。
PR TIMESなどのプレスリリース配信媒体を使って、手軽に配信できます。他社の事例がたくさん載っているので、参考になります。文面は、ChatGPTなどのAIツールを使うと、ある程度の下書きを出力してくれます。
まず大切なのは、メディアの動きを把握することです。実は、メディアが1年のうち報じるイベントは、ほぼ決まっているのです。お正月、成人式、バレンタイン、節分、花粉症の季節、春休み、ひな祭り、ホワイトデー、新生活、ゴールデンウィーク、子供の日、母の日……。こういったイベントに合わせて企画を考えて配信します。
あるお店では、バレンタインに合わせ、ところてんベースの商品「チョコろてん」を企画、リリース配信したところ、メディアに毎年取り上げられるようになりました。また、防災の日に合わせてプレスリリースしたあるお店では、20社ほどのメディアで紹介されました。
型破りな商品で注目を集める方法もあります。あるお店では、1枚3万円する「貴族のピザ」を企画しました。一般消費者向けではありませんでしたが、フォワグラやトリュフをふんだんに使った斬新さからテレビ番組で紹介され、「テレビで紹介された店」という実績を作ることができました。
諦めず、色んな角度からコツコツ試していくとよいでしょう。
効率化して、コツコツ取り組む
お店の運営で手一杯の状態で、フック集客を続けることは難しいでしょう。やると分かりますが、情報発信しながらモノを売るのは、ある意味「2つの仕事を並行してやる」ようなものです。情報発信しているお店は、お客さんからすると楽しそうに見えると思いますが、通常業務を賢く効率化しておくことが大前提なのです。まずは、商品の仕入れや在庫管理、受注処理など、基本的な業務をしっかりと整えた上で、気持ちに余裕が出てくれば、フック集客を始める時期です。
 坂本氏
坂本氏こういった情報発信をしていても、フォロワー数の増加は計測できますが、この活動でいくら売上につながった、といった明確な費用対効果はなかなか出しづらいですよね。だから、多くの人にとっては、気持ちが続きません。もしあなたが、損得抜きでこういった情報発信を楽しめる性格なら、それはお店にとってかなり大きな差別化要素かもしれません。
この記事は『売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則。』(インプレス刊)の一部を編集し、公開しているものです。
売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則。
坂本悟史 /コマースデザイン 著
インプレス 刊
価格 2,400円+税
ECの仕事を「販売・業務・組織・戦略」の 4分類に整理。現代のEC販売はもちろんのこと、仕入れ・製造から受注・出荷までのEC業務、AIやリモートを活用したEC組織運営、商品開発やブランディング、会計や経営計画などのEC戦略までをカバー。経営者の学び直し、担当者の育成、組織の共通言語におすすめです。